大学生活、なんだかうまくいかない。そんなふうに感じたこと、ありませんか?
友達のキラキラしたSNS投稿を見ては、自分との違いにモヤモヤしたり。
コロナ禍が明けて、周囲が動き出すなか、自分だけが置いていかれてるような不安に襲われたり。
特別なスキルも、実績もない「何者でもない自分」に、焦りを感じてしまったり。
そんな中で、見落とされがちなのが“自己肯定感”。
これは「自分は自分でいい」と思える心の土台のようなもの。
この土台がしっかりしていれば、少しの失敗や不安にも振り回されにくくなります。
だからこそ、今こそ大学生に「自己肯定感を高める習慣」が必要なんです。
この記事では、自己肯定感をゆっくり丁寧に育てるためのシンプルな習慣を3つご紹介していきます。
無理なくできて、じわっと心に効いてくるものばかりです。
第1章:自己肯定感が低い大学生の特徴とその背景

大学生活を送る中で、「なんとなく元気が出ない」「自分が嫌い」と感じる瞬間はありませんか?
何か特別な理由があるわけでもないのに、気づけば気持ちが沈んでしまっていたり。
周りが楽しそうに見えるほど、自分の現状にモヤモヤが膨らんでしまったり。
でも、こうした感情の背景には、ある共通した傾向があります。
それは「自己肯定感の低下」です。
そしてそれは、決してあなた一人の問題ではありません。
まずは、自分にどんな特徴や考え方のクセがあるのかを、やさしく見つめ直してみましょう。
この章では、自己肯定感が低くなってしまう大学生に多い傾向や、その背景を3つの視点から解説していきます。
無気力や倦怠感に悩まされる日々
やる気が出ない、何をしても楽しくない。そんな状態が続くと、自信も失われていきます。
朝起きてもベッドから出るのがつらい、何をしても「意味がない」と感じてしまう。
予定があっても、気持ちがついてこなくて結局キャンセルしてしまうこともあるかもしれません。
課題やレポートにも手がつかず、ただ時間だけが過ぎていく。
そういった日々が続くと、ますます「自分はダメなんだ」と感じる悪循環に陥ってしまいます。
でも、こうした感情は決して特別なものではなく、多くの大学生が一度は経験しているものです。
季節の変わり目や環境の変化、新しい人間関係の中で心が疲れてしまうのは自然なこと。
大切なのは、自分を責めすぎず「いまの自分はこういう状態なんだ」と受け止めてあげること。
その一歩が、自己肯定感を取り戻す大切なスタートになります。
周囲との比較で自分を否定してしまう
SNSやリアルな友人との比較で、劣等感を抱いてしまう人は少なくありません。
特にSNSでは、人の生活の「いいところ」だけが切り取られて投稿されています。
旅行、恋人、キラキラした友人関係、夢に向かって頑張る姿──そんな投稿を見ていると、「自分は全然ダメだ」と思ってしまうのも無理はありません。
また、大学生活では他人の成績や就活状況なども耳に入ってくることが多く、自分の状況と比べて焦る気持ちになることもあります。
実際は、人それぞれタイミングや得意不得意があるのに、なぜか「今この瞬間で比べてしまう」クセがついてしまうのです。
このクセは無意識のうちに心をすり減らしてしまい、自分の価値をどんどん低く見積もってしまう原因になります。
だからこそ、他人の状況を“自分を責める材料”ではなく、“ただの他人の物語”として見る視点がとても大切です。
他人の人生を眺めることと、自分の人生を否定することはまったく別もの。
この意識の切り替えが、自己肯定感を守る大きなカギになります。
理想が高いほど自分に厳しくなりがち
本当は真面目で頑張り屋なのに、自分に対してだけ評価が厳しくなってしまう傾向があります。
たとえば「もっとできるはず」「こんなことで満足していてはいけない」と、常に自分を追い込んでしまう。
小さな成功に目を向けるよりも、できなかったことや不足している部分にばかり注目してしまうんです。
それは向上心が強いともいえますが、度を超すと自分を傷つけてしまう原因にもなります。
理想を高く持つこと自体は悪いことではありません。
でも、今の自分を認めることができなければ、どんなに理想を叶えても満足感は得られないものです。
「今の自分も悪くない」と思えるようになることが、結果的にもっと自分を成長させるエネルギーになります。
まずは、自分に対する“優しさの視点”を持ってみることから始めてみてください。
他人には優しくできても、自分にだけは厳しくなってしまう──そんな人こそ、自己肯定感を高める習慣が大切なのです。
第2章:習慣①「自分を認める日記」を書く
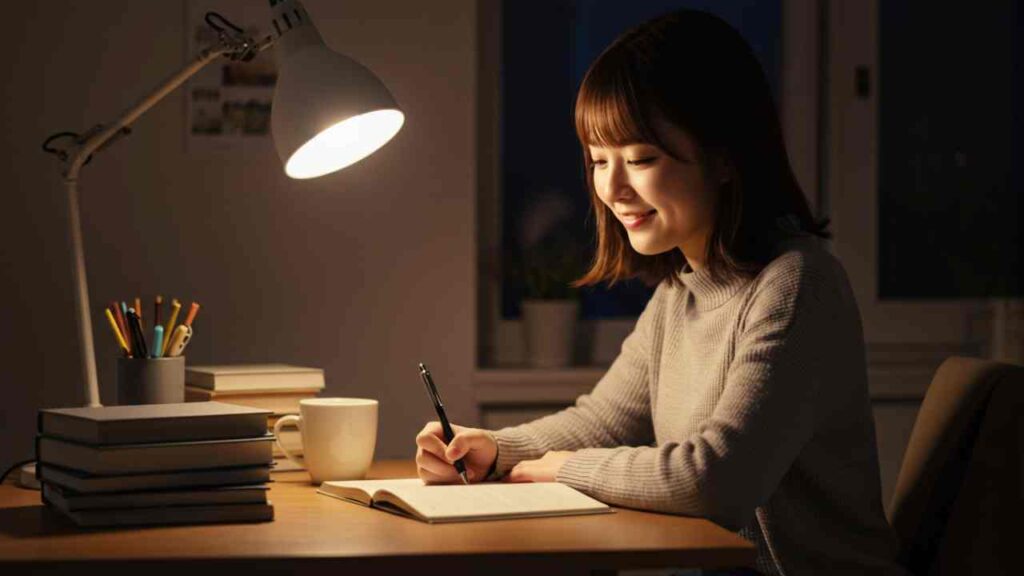
「自己肯定感を高めたい」と思っても、急に前向きになるのは難しいもの。
でも、ほんの少し、自分を“認める練習”をするだけで、心はゆっくりとほぐれていきます。
その第一歩にぴったりなのが「できたこと日記」。
忙しい毎日の中でも、自分のちょっとした頑張りを見つけて書き出すだけ。
それだけで、「私、今日ちゃんとやってたんだな」と思える瞬間が増えていきます。
この章では、日記習慣のやり方や、続けやすくするためのアプリ紹介、心への効果などを具体的に紹介していきます。
今日からできる小さな変化を、ぜひ感じてみてください。
1日の終わりに「できたこと」を3つ書く
たとえ小さなことでも、自分の行動を言葉で記録することが大切です。
この習慣は、自分に「よくやったね」と声をかけるようなもの。
普段はスルーしてしまうようなことでも、書き出すことで自分の頑張りに気づけるようになります。
「授業に遅れずに出席できた」「洗濯を片づけた」「友達に優しい言葉をかけた」など、本当に些細なことでOK。
大切なのは、完璧さを求めるのではなく、“できたこと”に意識を向ける姿勢です。
1日の終わりにこの作業をすることで、今日の自分を「悪くなかった」と肯定する感覚が育っていきます。
書く時間帯は、寝る前の5分がベスト。
スマホのメモアプリや紙のノート、形式はなんでも構いません。
毎日の小さな記録が、やがて「私、意外と頑張ってるじゃん」という実感につながっていくはずです。
成功体験を積み重ねる力を意識する
自分を認める感覚は、日々の中で少しずつ育まれていきます。
特に、何かをやり遂げたという達成感は、自己肯定感を大きく後押ししてくれます。
とはいえ、「大きな成功」でなくても大丈夫。
朝の早起きや、面倒な手続きを終えたこと、友達に声をかけたことなど、小さな行動にもちゃんと意味があります。
それらを記録して「できた」と振り返ることで、自分への信頼が少しずつ芽生えてきます。
また、記録を続けていくと、自分が何を頑張ってきたのかが可視化されるため、後から読み返したときにもモチベーションの源になります。
たとえ落ち込んだ日があっても、「過去の私はこんなに頑張っていた」と思い出せる材料になるのです。
成功体験を日常に見出す視点を持つことは、自己肯定感の貯金をしていくようなもの。
意識的にポジティブな瞬間に光を当てていくことで、自分の価値を再確認できるようになります。
続けやすいおすすめ日記アプリ紹介
毎日書く習慣が大切とはいえ、なかなか続けられない…という人も多いはず。
そこで活用したいのが「日記アプリ」。
スマホで手軽に記録できるだけでなく、振り返り機能やリマインダー機能もあるので、習慣化がぐっとしやすくなります。
ここでは、初心者でも続けやすい、おすすめの日記アプリを3つご紹介します。
- Daylio:気分のアイコンと簡単なメモだけで記録が完了。毎日の気分の変化をグラフで確認でき、自己分析にも最適。
- みんチャレ:仲間と一緒に目標を続けるスタイル。日記だけでなく、勉強や運動など他の習慣とも併用しやすい。継続力に不安がある人におすすめ。
- Moodnotes:心理学ベースで感情を丁寧に記録できるアプリ。思考のクセを視覚化してくれる機能もあり、心の整理がしやすくなります。
それぞれ使い勝手やデザインが違うので、自分に合うものを選んでみてください。
紙の日記と違って荷物にならず、スキマ時間にも活用できるのがアプリのいいところ。
「習慣化って難しそう…」と思っていた人も、アプリの力を借りればぐっとハードルが下がりますよ。
第3章:習慣②「人と比べないSNSの使い方」

SNSを開くと、なんだか心がザワザワする。
友達のキラキラ投稿に、焦ったり落ち込んだりした経験、ありませんか?
そんなときこそ、SNSとの付き合い方を見直すチャンスです。
情報に飲まれるのではなく、自分の心を守るための“使い方”を身につけることが、自己肯定感を守るカギになります。
この章では、SNSで落ち込まないための環境づくりや、心の余裕を取り戻す工夫、実際の体験談などをご紹介します。
「見る・見ない」を自分で選べるようになることで、心にやさしい時間が増えていきますよ。
フォロー・ミュートの整理で心に余白を
見るたびに疲れるアカウントは、思い切って整理してOK。
SNSは、情報が多すぎて“見るだけで疲れる”状態になってしまうことがあります。
特に、完璧すぎるライフスタイルや、美しすぎる写真ばかりが並ぶタイムラインは、無意識のうちに「自分との違い」を意識させてきます。
その結果、「自分には足りないものが多すぎる」と感じて、どんどん自己肯定感が削られていってしまうんです。
そんなときは、心のメンテナンスのつもりでSNSのフォローやミュート機能を活用してみましょう。
他人の投稿に振り回されるのではなく、自分の心を守るためのフィルターをかける。
たとえば、見ていて不安になる投稿や、なんとなくイライラしてしまうような投稿は、思い切って一度距離を置くのが◎。
情報を選ぶことは、今の自分を大切にする行動です。
SNSとの付き合い方を変えることで、心に余白が生まれ、少しずつ自分に優しくなれるようになります。
SNSを見る時間を決めて制限する
夜だけオフにする、1日○分までなど自分ルールを設けてみましょう。
時間を区切って使うことで、SNSに振り回される時間を減らすことができます。
たとえば、「朝起きてから1時間は見ない」「就寝前2時間はSNSをオフにする」といったルールは、脳の疲労軽減にもつながります。
また、通知をオフにすることで、無意識にアプリを開いてしまう癖を減らす効果も。
SNSを見すぎてしまう原因は、“ついなんとなく開いてしまう”ことが多いので、視覚的なトリガーを遠ざける工夫も大切です。
アプリの使用時間を制限できる設定や、時間帯で自動的にブロックできるツールも活用すると、より効果的にコントロールできます。
こうした自分ルールは、最初はちょっと面倒に感じるかもしれませんが、慣れてくると「SNSがない時間」の心地よさに気づくようになります。
自分の時間を取り戻すことは、心のリズムを整える大切なステップです。
デジタルデトックスの実践例と効果
- 散歩を習慣にすることで、自然の中で心がほぐれ、考えごとが整理されるようになったという声も多いです。歩きながら深呼吸するだけでも、ストレスが軽くなる感覚が得られます。
- SNS断ちで気分が前向きに変化したという人も。毎日欠かさず見ていたSNSを1日オフにするだけでも、頭がすっきりしたり、他人と比べない安定感が生まれます。
- 自分の時間が取り戻せた実感があると、読書や趣味、部屋の片付けなど「本当にやりたかったこと」に時間が使えるようになったという嬉しい変化も。
- 実際に「SNSをやめてから睡眠の質が上がった」「集中力が持続するようになった」といった効果も報告されています。
- デジタルから少し離れることで、自分の内面に目を向けられるようになり、結果的に自己肯定感がゆっくりと育っていくきっかけにもなります。
第4章:習慣③「小さな成功体験を積む挑戦をする」
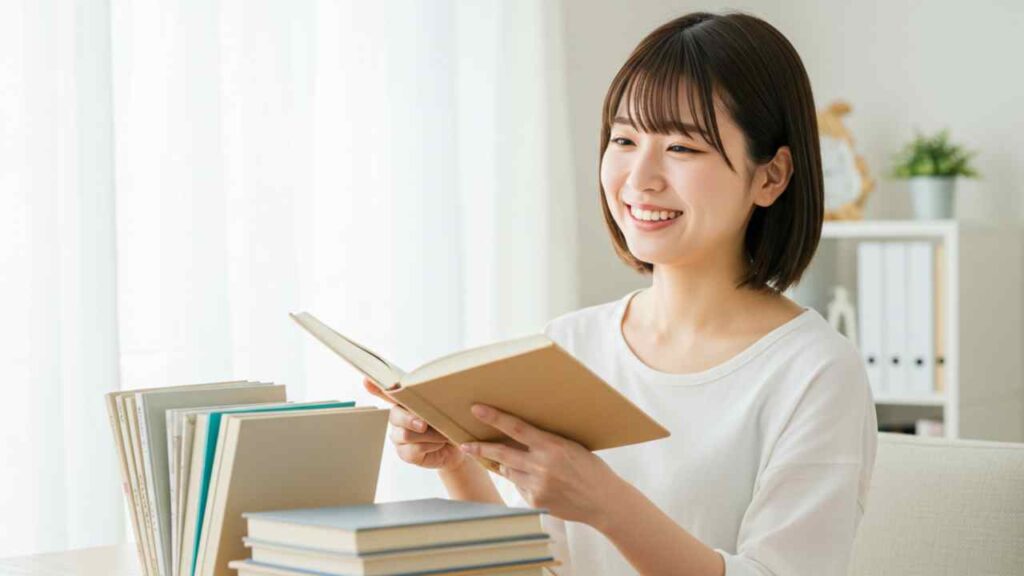
「やってみたけど、うまくいかなかったらどうしよう」
そう思って何も始められないこと、ありますよね。
でも実は、ちょっとした挑戦こそが、自信の種になるんです。
成功体験といっても、大きな成果じゃなくていい。
「やってみよう」と動いたその気持ちが、自己肯定感をじわじわ育ててくれます。
この章では、日常の中で見つけられる“小さなチャレンジ”のヒントと、それが心にもたらす効果について、実例を交えてお届けします。
「自分にもできたかも」と思える瞬間を、増やしていきましょう。
日常の中でできるチャレンジを見つける
大きなことではなく、まずは身近な一歩から始めましょう。
「チャレンジ」と聞くと、何か大きな目標に立ち向かうようなイメージを抱きがちですが、実はほんの些細なことでも十分です。
たとえば、普段より少し早起きして朝の時間にストレッチをしてみる、いつもと違う道で大学まで歩いてみる、学食で新しいメニューに挑戦してみる──そんな一見小さなことでも、「やってみた」経験が自己肯定感を育てるきっかけになります。
日々の中にあるちょっとした「未体験」を見つけて、そこに一歩踏み込むことが重要です。
新しいことを試すたびに、「自分にもできた」という感覚が蓄積されていきます。
やがてその小さな自信が連鎖し、大きな挑戦へのステップにもつながるようになるのです。
まずは「昨日とは少し違う今日」を意識して、変化を楽しむ心を育てていきましょう。
自己肯定感と成功体験の関係
小さな「できた」が心の支えとなり、自信につながります。
たとえば、「今日は電車に乗って外出できた」「初めてひとりでカフェに入った」「苦手なレポートに手をつけられた」──こうした行動は一見ささやかに見えますが、実は大きな意味を持っています。
成功体験というのは、決して表彰されるようなことや、誰かに褒められることだけではありません。
「自分で決めたことを、やってみた」「不安だったけど行動できた」と感じること自体が、立派な成功体験です。
こうした経験は、まるで“心の貯金”のように、自信という名の資産を少しずつ増やしてくれます。
そしてその貯金は、次に新しいことに挑戦するときの勇気や、落ち込んだ時に自分を支える柱になってくれるのです。
小さな成功の積み重ねが、「私にもできる」という実感を育て、やがてそれが自己肯定感の強さへと変わっていきます。
行動が未来を変える具体例
- 簿記や英検の勉強を始める:まずは参考書を1冊用意して、1日10分だけ机に向かうことから始めてみましょう。勉強を習慣にできれば、「努力する自分」に自信がついていきます。
- noteやSNSで発信してみる:自分の好きなこと、学んだこと、思ったことを発信する場を持つと、自分の考えを整理でき、思わぬ共感が得られることも。人とのつながりが、やる気や自信につながることもあります。
- バイトやサークルでの新しい経験:接客やイベントの企画運営など、新しい環境での挑戦は、視野を広げる大きなチャンス。失敗を恐れず飛び込むことで、「思ってたよりできた!」という成功体験が得られます。
- プレゼンやゼミでの発言にチャレンジ:緊張しても大丈夫。発言できたこと自体が立派なステップです。積極性は自己肯定感の源になります。
- ひとり旅や短期留学に挑戦する:知らない場所で自分と向き合う体験は、自己理解を深めるうえで大きな意味を持ちます。小さな一歩からでも十分です。
どんな行動も「やってみよう」と思えた時点で、すでに自己肯定感の芽が育ちはじめています。
終章:大学生活は“自己肯定感”を育てる最高の時期

大学生という今の時期は、実は「自分を育てる」最高のタイミング。
勉強や遊び、出会いや失敗──すべてが、自分という人間の輪郭をつくっていく貴重な材料です。
焦らなくていい。誰かと比べなくていい。
自分のペースで、自分の気持ちと向き合いながら、一歩ずつ進んでいけば大丈夫。
この章では、大学生活の中で“自己肯定感”を育む意味と、そこから得られる気づきや未来へのつながりについてお伝えします。
あなたの毎日が、少しでも軽やかになりますように。
自分と向き合う時間を大切にする
他人ではなく、自分の軸をしっかり持つことが未来につながります。
大学生活は、自由な時間が多い分、自分と向き合えるチャンスにもあふれています。
この時期に「私はどんなことが好きで、何をしていると心地いいのか?」をゆっくり見つけていくことが、自分の軸づくりにつながります。
スマホやSNSから少し離れて、何も考えずにぼーっとしてみる時間も意外と大切。
散歩をしたり、手帳に思いを綴ったり、一人でカフェに行って本を読んだり──そんな小さな“ひとり時間”の積み重ねが、自分の輪郭をはっきりさせてくれます。
他人の期待や基準ではなく、「自分はどう感じて、何を大切にしたいのか」を探る時間を、ぜひ意識して持ってみてください。
焦らず、比べず、歩いていく
他人のペースに振り回されず、自分のスピードで進むことが大切です。
SNSやまわりの友達が、どんどん先に進んでいるように見えると、「私も早く何かしなきゃ」と焦る気持ちになってしまうもの。
でも、人生のペースは人それぞれ違っていて当たり前。
早く結果を出す人もいれば、じっくり時間をかけて進む人もいます。
大切なのは、どのタイミングで何をするかではなく、「今の自分がどんな気持ちで歩いているか」。
立ち止まって深呼吸することも、ゆっくり歩くことも、時には引き返すことだって、すべて自分にとって意味のあるプロセスです。
他人のスピードに焦って疲れてしまうより、自分に合った歩幅で一歩ずつ進んでいく方が、心にとってずっと優しい選択です。
焦らないことで見える風景、比べないことで気づける自分の魅力──それらを大切にしながら、あなただけのペースで歩んでいきましょう。
今からでも遅くない、小さな一歩を踏み出そう
今日できることから始めてみる。それが変化のきっかけになります。
「こんな自分じゃダメだ」と思ってしまう日があったとしても、そこで終わりではありません。
むしろ、そんな自分に気づけたことが、第一歩のサインです。
たとえば、今日できること──部屋の片づけ、早めの就寝、誰かにありがとうを伝えること──それだけでも立派な一歩です。
変わろうと思う気持ちがある限り、人はいつでも成長できます。
最初の一歩は小さくて構いません。
でも、その一歩を積み重ねていくことで、少しずつ自分が好きになっていくはず。
「今日の自分、ちょっといいかも」そう思える瞬間を、増やしていきましょう。
その積み重ねが、未来のあなたをきっと支えてくれます。


