春の訪れとともに、軒先に現れるツバメたち。 その姿を見て「春が来たな」とほっこりする方も多いでしょう。 けれど最近、こんな声を聞くことが増えました。
「ツバメの巣、正直ちょっと困るんです…」
そう感じる理由は、人それぞれ。 でも、その背景には“地域ごとの文化や価値観の違い”があるかもしれません。
ツバメが巣を作ると幸運が訪れる──そんな言い伝えが残る一方で、 フンや鳴き声、建物の汚れといった現実的な問題に悩まされる人もいます。
「歓迎する地域」「避けたい地域」
なぜ分かれるのか? 何が境界線なのか?
この記事では、ツバメの巣が“喜ばれる場所”と“嫌われる場所”の違いを、 風習・法律・住民トラブル・共存の工夫など、多角的に掘り下げてご紹介します。
読めばきっと、「あ、うちの地域にも当てはまるかも…」と気づくことがあるはず。
最後まで読むことで、あなた自身がツバメにどう向き合うか、 そのヒントが見えてくるはずです。
ツバメの巣を嫌う理由とは?背景を整理

ツバメの巣って、どこかほっこりするイメージがありますよね。
でも実際に自宅やお店の軒先に作られると、ちょっと困ってしまうことも。
巣の下にフンがたまったり、壁が汚れたり、見た目も衛生面もちょっぴり気になる…。
さらに、そこに虫や他の動物まで寄ってきたら?
ツバメの存在が、思わぬトラブルの原因になることもあるんです。
この記事では、ツバメの巣が敬遠される理由について、
「どうして嫌がられるの?」「どんな問題があるの?」を、
衛生・建物・害虫という3つの視点から分かりやすく解説していきます。
衛生面の懸念 ─ 糞や寄生虫、悪臭のリスクから敬遠されるケース
春から夏にかけて、ツバメは民家や商店、公共施設などの軒先に巣を作る光景が見られます。
その様子はどこか親しみやすく、日本の初夏を感じさせる風物詩として受け入れられてきました。
小さなヒナが親鳥を待つ姿には、命の営みの尊さを感じるという声もあります。
けれども、現実的な問題として、ツバメの巣の下には糞が集中して落ちるため、通行人にとって不快な状況が生じることもあります。
糞には雑菌や寄生虫が含まれている場合もあり、衛生的な観点から不安を感じる人も少なくありません。
特に梅雨時期には湿度が高く、悪臭がこもりやすくなるため、臭いや汚れが一層気になるという声もあります。
人の出入りが多い施設、たとえば病院や幼稚園、飲食店などでは、感染症への配慮も含めて対応が求められるケースが増えています。
たとえ小さな巣であっても、トラブルの要因になりうると判断される場合もあるのです。
さらに、通学路や保育施設周辺など、小さなお子さんやベビーカー利用者が多い場所では、落下した糞が衣服や持ち物を汚す可能性もあり、より強い衛生対策の必要性が生まれます。
このように、かわいらしい存在として見られる一方で、日常生活の中で現実的な課題を引き起こすことが、ツバメの巣を歓迎できない理由のひとつになっているのです。
建築・設備への影響 ─ 巣による汚れや建材への影響
ツバメの巣は、泥や枯れ草、小枝など自然素材を巧みに使って作られます。
一見すると自然の造形美にも思えますが、設置される場所によっては深刻な問題の原因になることもあります。
たとえば、外壁や看板、軒天井、さらには防犯カメラや照明器具の真上に作られるケースもあり、泥や巣材が付着して美観を損ねてしまいます。
特に白や淡い色の外壁では、汚れが目立ちやすく、クリーニングや補修が頻繁に必要になります。
また、雨に濡れた泥は乾燥するとこびりついてしまい、落とすのに高圧洗浄などの専門的な作業が求められることも。
外壁塗装の劣化や金属部分のサビの原因になることもあり、建物の維持管理コストが増える要因となります。
巣が作られる位置が高所であることが多いため、清掃や撤去には脚立や足場が必要となり、作業が大掛かりになってしまいます。
特に高齢者のみの家庭や、管理者が常駐しない店舗では、対応が後手に回りやすく、被害が広がってしまうこともあります。
こうした理由から、事前に巣作りを防ぎたいと考える人も増えており、「ツバメに悪意はないけれど、実害が大きいから」といった複雑な思いを抱えるケースも少なくないのです。
害獣・害虫の誘因 ─ 天敵(カラス・ヘビ)やダニ等の発生が心配
ツバメの巣にヒナがいると、その存在を察知したカラスやヘビが寄ってくることがあります。
カラスは非常に知能が高く、エサを探して集団で行動することもあり、ツバメの巣を狙って執拗に襲撃を試みます。
その際、親鳥がカラスに立ち向かおうとして空中で争う場面もあり、鳴き声や羽ばたき音が大きな騒音となって近隣の迷惑になることも。
また、ヘビがツバメの巣に忍び寄り、ヒナや卵を狙うケースも報告されています。
ヘビが軒下や壁を這って登る様子は、住人にとって非常に恐怖を感じさせるものであり、衛生面以上の精神的ストレスとなる場合もあります。
さらに、巣の内部にダニやノミなどの害虫が発生することも。
こうした害虫は、風通しのよい場所にある巣から室内へと移動してしまうことがあり、人間の皮膚にかゆみや赤みなどのトラブルを引き起こす原因になります。
特に、小さなお子さんやペットがいる家庭では、アレルギーや皮膚疾患への影響が懸念されます。
これらのリスクを避けるために、あらかじめツバメの巣作りを防止する措置を講じる家庭や、施設側で軒下に物理的なガードを施すケースも増えています。
「ツバメを傷つけたいわけではないけれど、生活の安心・安全を守るためには共存が難しい」と感じる人々が一定数いるのも事実です。
ガムテープでの対処法も まとめました。↓
地域ごとのツバメ忌避の風習と慣習

同じツバメなのに、ある地域では「幸運のしるし」として大歓迎されるのに、
別の地域では「フンが汚いから」と忌み嫌われてしまう。
その違いって、いったいどこから来るのでしょうか?
都会と田舎、商店街や飲食店、そして自治体ごとの対応の違い。
実は、ツバメをどう受け入れるかには、地域性が大きく関わっているんです。
この章では、ツバメに対する対応がどう変わるのか、
背景にある風習や慣習をひもときながら、具体的な事例とともにご紹介します。
都会vs田舎の対応差 ― 都市部では衛生優先、田舎では縁起重視
ツバメに対する受け止め方は、地域によって大きく異なります。
都市部では、衛生面や建物の美観が重視される傾向が強く、ツバメの巣による実害を懸念して、巣作りを防止する対策が積極的に取られることが多いです。 特に商業施設や駅周辺では、フン害や騒音への配慮から、忌避の姿勢がはっきりと表れることもあります。
一方、地方の農村部や観光地などでは、ツバメは「福を運ぶ鳥」「豊作の前触れ」などといった縁起物として歓迎される文化が根強く残っています。 巣ができると「今年も良いことがある」と前向きに捉える声も多く、地域ぐるみで温かく見守る風土が今も残っています。
このように、生活スタイルや地域文化の違いが、ツバメへの対応に明確な差を生んでいるのです。
商店・飲食店での対応例 ― 巣を壊すと客足が減るという都市伝説も
ツバメの巣と商売繁盛を結びつける「縁起」もまた、日本各地に存在しています。
特に老舗の和菓子屋や旅館、飲食店などでは、「ツバメが来る=お客が来る」という言い伝えが残っており、巣を壊すことを避ける傾向があります。 ある地域では、ツバメの巣を壊した店舗が数ヶ月後に閉店したという話が噂になり、「縁起を無視したからだ」と語られることもあるほどです。
もちろん、科学的根拠があるわけではありませんが、こうした地域の空気感がツバメへの寛容な対応につながっています。 逆に、同業者同士でもツバメの巣をどう扱うかで判断が分かれ、店の評判や雰囲気に影響を及ぼすことも。
「ツバメが来る家はなぜ幸せなのか?」も まとめました。↓
自治体による違い ― 鳥獣保護法に基づく対応や許可制の有無
ツバメは「鳥獣保護管理法」によって守られているため、巣や卵、ヒナをむやみに撤去することは法律で禁じられています。
しかし、その運用は自治体ごとに若干異なり、対応に差があるのも現実です。
ある市では「フン被害への苦情が多い場所に限り、巣立ち後の撤去に助成金を出す」という制度を設けていたり、別の地域では「撤去には事前申請が必須」と明確に定められている場合もあります。 また、近年では「住民とツバメの共生」を目指す施策として、フン受けの設置支援や啓発チラシの配布を行う地域も増えています。
このように、同じ日本国内でも、ツバメに対する規制や扱いは統一されておらず、住む地域によって大きな違いがあることを知っておく必要があります。
鳥獣保護法に基づく規制と地域対応
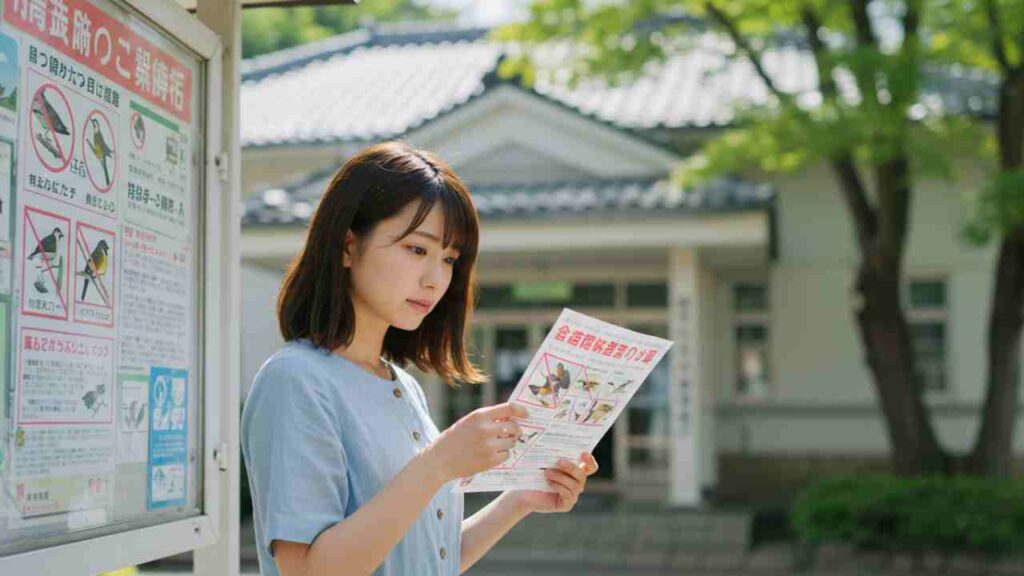
「ツバメの巣、勝手に壊してもいいの?」
そんな素朴な疑問に答えるには、法律の知識が必要なんです。
ツバメは日本の「鳥獣保護法」に守られているため、
その巣や卵、ヒナに対して勝手な行動はできません。
でも実際には、「空き巣なら撤去OK」という話もあって、少しややこしい…。
この章では、鳥獣保護法の基本ルールから、地域による違いや、
撤去の許可が必要なケースまで、わかりやすく解説します。
巣や卵・ヒナの撤去は禁止 ― 地域ごとの行政対応の実情
ツバメは「鳥獣保護管理法」により、法律で保護されている野鳥のひとつです。 このため、繁殖期にある巣や、卵・ヒナが存在する場合の撤去・破壊行為は原則として禁止されています。
たとえ自宅の軒先であっても、勝手に取り除いてしまうと法に触れる可能性があり、知らずに違反してしまうケースも後を絶ちません。 特に都市部では通報や監視体制も整っており、無許可での対応が問題視されることも。
自治体によっては、市民向けに「ツバメの扱いに関する注意点」や「鳥獣保護法の周知リーフレット」などを配布しているところもあります。 地域ごとに情報提供や相談窓口が整備されつつあり、個人で判断せず専門窓口に相談することが大切です。
巣立ち後なら撤去OK? ― 空き巣撤去の手続きと地域差
基本的に、ヒナが巣立って完全に使用されていない状態であれば、ツバメの巣を撤去することは可能とされています。 この「空き巣」扱いの基準は明確ではなく、地域や行政によって対応の仕方が異なるため注意が必要です。
たとえば、「最後のヒナが巣立ってから1週間以上経過した状態」を目安とする自治体もあれば、「親鳥の出入りが完全に確認できなくなってから」と定める場合も。 中には、念のため市役所や保健所などの環境課に確認し、書面で許可を取るよう指導する地域も存在します。
心配な場合は撤去前に写真を撮っておく、地域の窓口に連絡を入れてから作業を行うなど、慎重な対応が推奨されます。
許可取得が必要な自治体ルール ― 具体的な手続き事例
ツバメの巣を撤去する際、時期や状態にかかわらず許可申請が必要とされる地域も存在します。 特に「集団で営巣する傾向が強い場所」や、「文化財・公共施設などの特定地域」においては、より厳しい対応が求められる傾向があります。
たとえば、●●市では市役所の環境政策課に「撤去申請書」を提出し、担当職員の現地確認を受けることで許可が下りる仕組みになっています。 また、申請時には撤去理由や巣の場所、写真の提出が求められ、「やむを得ない理由」でない限りは許可が下りないこともあります。
このような自治体ルールに基づく規制がある一方で、申請手続きの簡素化を図っている地域もあり、対応は千差万別です。 大切なのは、ツバメの命や文化的価値を尊重しつつ、自分の住む地域のルールに従って丁寧に対応するという姿勢です。
避ける地域と受け入れる地域、その境界線

ツバメを避ける人と、受け入れる人。
その価値観の違いは、どこからくるのでしょうか?
「フンで汚れるからNG」「いや、福を呼ぶ鳥だから残したい」
そんな声が混在するなかで、地域によってはトラブルになることも。
この章では、都市部や店舗中心の「忌避派」、
農村部や観光地の「歓迎派」、そしてその間で揺れる“グレーゾーン”について、
それぞれの特徴や考え方の違いを解説します。
衛生・快適性重視地域 ― 都市部・店舗中心で忌避する傾向
都市部では、人の往来が多く、清潔さや景観が重視される環境のため、ツバメの巣は歓迎されにくい傾向にあります。
特に新築の住宅街や、美観を保つことが重要な商業エリア、飲食店が並ぶ街並みでは、フンによる汚れやにおいがクレームの原因になることも。
そのため、軒先にネットやテグスを張る、巣の材料となる泥をまき散らす場所を掃除するなど、ツバメの巣作り自体を事前に防ぐ取り組みが進んでいます。
また、マンション管理組合などでも「巣を作らせないように」と周知がされているケースもあり、組織的にツバメ忌避の方針を取ることも珍しくありません。
このような地域では、「自然との共生」よりも「生活の快適さ」を優先する傾向が見られます。
縁起・益鳥として重視地域 ― 田舎や観光地で歓迎・保護する動き
一方で、農村部や自然が多く残る地域、観光地などでは、ツバメを「縁起の良い鳥」「益鳥」として受け入れる文化が根強く残っています。
田畑が多い地域では、ツバメが害虫を食べてくれる存在として重宝され、「ツバメが巣を作ると豊作になる」との言い伝えもあります。
また、温泉地や歴史的な町並みのある観光エリアでは、ツバメの姿そのものが風情ある景観の一部とされ、地域ぐるみで保護活動をしているケースもあります。
フン受けの設置や清掃の手伝いを住民が行うほか、子どもたちが巣立ちを見守るような教育活動に発展することもあり、ツバメと地域の絆が強いのが特徴です。
二律背反の現場事情 ― 「歓迎」vs「忌避」の現場で起きる調整や問題
ツバメを「守りたい」と思う人と、「遠ざけたい」と思う人が同じ地域内に混在することで、対応が難しくなることもあります。
たとえば、同じ商店街の中でも、ある店は「ツバメが来ると客足が増える」と喜び、別の店は「汚れて困る」と不満を持っているケースも。
また、住宅地でも「子どもがツバメを楽しみにしている」という家庭と、「アレルギーが心配だから近づけたくない」という家庭が並んで住んでいることもあります。
このような場合、地域での話し合いやルール作りが必要になりますが、感情や価値観が絡むため調整が難航することもあります。
自治体によっては、共存を目指すためのガイドラインやフン受けの配布支援など、中立的な対応策を進めているところもあり、今後ますます「地域の合意形成」が鍵となっていくでしょう。
実際の「忌避地域」の声まとめ

「ツバメって迷惑…」そんな本音、なかなか言いづらいですよね。
でも実際には、ツバメによる被害やトラブルに悩まされている人も多いのです。
この章では、商店街での苦情、住宅地での隣人トラブル、
そして自治体が介入した対応例など、リアルな「忌避地域の声」を集めてみました。
現場の声を聞くことで、ツバメと共に生きることの難しさや、
それでも共存を模索する姿勢の大切さが、きっと見えてくるはずです。
商店街での「駆除」派の声 ― フン被害で店舗名が出ない事例を紹介
ある都市部の商店街では、ツバメの巣が看板や軒先に集中して作られるようになり、フンの被害に悩む店舗が続出。 特に飲食店では「看板が汚れて読めない」「外壁のシミがひどくてイメージダウンにつながる」といった声が上がっています。
中には「店舗名がツバメのフンで隠れてしまい、初めて来たお客さんが通り過ぎてしまった」という事例もあり、経営に直結する問題として取り上げられています。
結果として、商店会の中で“巣の撤去を積極的に進めるべきかどうか”について議論が生じ、忌避派と共存派で意見が割れる場面も見られました。
住宅地でのトラブル事例 ― 隣人との摩擦やクレーム記録
住宅地では、ツバメの巣があることで隣人間のトラブルが発生することもあります。 「ツバメの巣が隣の家にあるのに、フンは我が家の駐車場に落ちてくる」「ベランダが使えなくなった」といった苦情が自治会に寄せられるケースも。
中には、掃除の負担が一方的になり「なぜウチばかりが対応しなければならないのか」と不満が蓄積する例や、「勝手に巣を撤去された」といった感情的なトラブルに発展することも。
こうした問題が積み重なることで「次の年はツバメを寄せつけないようにする」といった流れが生まれ、忌避ムードが強まることがあります。
自治体・行政の対応実例 ― 注意喚起・取り締まりの流れ
ツバメに関する地域の苦情が増加したことを受けて、自治体が対応に乗り出した例も報告されています。
たとえばある市では、「ツバメの巣に関する注意とお願い」という掲示物を掲示板に貼り出し、無断撤去の禁止やフン対策の啓発を行いました。 また、環境課が地域を巡回し、ツバメの巣の状態や住民の声を記録するケースもあります。
一部では「苦情が多発する地域に限り、巣立ち後の巣撤去を助成対象にする」という制度を導入するなど、現場のバランスを取る工夫が見られています。
ただし、自治体の姿勢や予算、人員の違いにより対応には差があり、「うちの地域では何もしてくれない」と不満を漏らす住民もいるのが実情です。
ツバメと共存するための地域別マナーと対策

「ツバメは好きだけど、やっぱりフンは困る…」
そんなジレンマを抱えている方は多いはず。
この章では、フン受けの設置や掃除の工夫、
光やテグスを使った自然にやさしい予防法、
さらに、地域ルールに配慮した対応まで、
ツバメと穏やかに共存するための具体策をご紹介します。
大切なのは、排除ではなく「うまく付き合う」こと。
あなたの地域にも、できることがきっとあります。
衛生対策グッズの導入 ― フン受け・掃除台設置法
ツバメの巣を完全に排除するのではなく、うまく共存していくためには「衛生対策」が欠かせません。
もっとも実践的なのが、市販されている「フン受けシート」や「専用トレー」の活用です。 軒下や巣の下に設置することで、フンが地面や壁に落ちるのを防ぐことができ、掃除も簡単になります。
また、掃除しやすいように脚立や拭き取り棒を常備したり、ペットボトルを使った簡易的な受け皿を工夫する家庭もあります。 定期的な清掃とともに、近隣住民に「ツバメがいるので多少のご理解を」と一言添えることが、トラブル防止にもつながります。
予防策(テグス・光を使う忌避法)― 自然な共生を目指す方法
ツバメの巣作り自体を未然に防ぎたい場合、物理的な予防策が効果的です。
代表的なのが「テグス(釣り糸)」を軒先に張る方法。 ツバメは糸があるとバランスをとりにくいため、その場所を避けるようになります。 透明で目立ちにくいため、見た目も損なわれにくいというメリットがあります。
また、光を反射するCDやアルミテープを吊るすことで、ツバメが警戒して寄りつかなくなるケースもあります。 ただし、やりすぎると他の鳥や住人にストレスを与える可能性もあるため、あくまで「バランス」を意識することが大切です。
地域ルールに配慮した共存の進め方 ― 許可取得・住民理解の得方
ツバメとの共存を円滑に進めるためには、個人の工夫だけでなく「地域の合意形成」も重要です。
たとえば自治体によっては、ツバメに関する注意点を明文化したガイドラインを発行していたり、撤去・保護のルールを住民説明会で共有しているところもあります。
そうした地域では、巣ができた際に「どう対応するか」を近隣住民同士で相談する文化ができており、感情的なトラブルが起きにくくなっています。 また、子どもたちへの環境教育の一環としてツバメの観察を促すなど、地域全体で見守る姿勢を育む取り組みも広がっています。
共存のためには、「自分だけで判断しない」「人にも鳥にも優しい選択を」が合言葉になるのではないでしょうか。
まとめ:忌避と歓迎のバランス

ツバメに対する考え方は人それぞれ。
「幸運のしるし」と思う人もいれば、「厄介な存在」と感じる人もいます。
でも大切なのは、どちらの考えも否定しないこと。
この章では、これまでの内容をふりかえりながら、
ツバメと人とが共に生きるための“やさしいバランスの取り方”について考えます。
「どうするのが正解?」ではなく、「何を大切にしたいか」。
あなた自身の気持ちにそっと寄り添う、そんなまとめをお届けします。
ツバメは長いあいだ「春の使者」として親しまれてきた存在でありながら、現代の生活環境や価値観の変化によって、歓迎される場面と忌避される場面がはっきりと分かれるようになってきました。
衛生面や建物への影響を考えれば、ツバメの巣作りに対して慎重にならざるを得ないというのも理解できます。 一方で、地域文化や自然との共生を重んじる人々にとっては、ツバメの訪れは喜ばしい出来事でもあります。
大切なのは、一方的に「排除」か「保護」かを決めつけるのではなく、それぞれの地域事情や住民の立場に寄り添った対応を考えることです。
忌避と歓迎、両方の声があるからこそ、共存のための工夫やルール作りが求められています。 物理的な対策だけでなく、思いやりと配慮のあるコミュニケーションもまた、ツバメと人が共に暮らす鍵となるでしょう。
もしあなたの家にツバメが来たなら── それを「問題」として受け止めるのか、「ご縁」として受け入れるのか。 その判断の前に、まずはこの記事を通して得た知識と周囲の声に耳を傾け、いちばん優しい選択をしていただけたら嬉しく思います。




