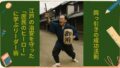「有志一同って、どう書けば正解なの?」
職場やPTA、サークルなどで誰かの退職祝いや香典をまとめることになったとき、真っ先に頭に浮かぶこの疑問。でも調べてみると、書き方やマナーは意外と細かくて、しかも場面によってルールも違う。
「名前の順番ってどうするの?」「金額って書くべき?」「“有志一同”って香典に使っていいの?」……こんなふうに不安と迷いで手が止まった経験、ありませんか?
実は、有志一同リストには「これだけ守ればOK!」という基本の型とマナーが存在します。しかもそのリストは、単なる名簿ではなく、参加者全員の想いや誠意を形にする大切なツール。正しく丁寧に作れば、渡す相手に気持ちが伝わり、トラブルも未然に防げます。
この記事では、有志一同リストの正しい書き方・マナー・テンプレート実例・オンラインでの効率的な作成法までを網羅し、香典・退職祝い・記念品などあらゆるシーンに対応できる実践ガイドとしてまとめました。
「恥をかきたくない」「失礼になりたくない」「サクッと正しいものを作りたい」——そんなあなたのために、忙しい中でもパッと読めてすぐ使える内容になっています。
あなたのそのリストが、誰かの心にしっかり届くように。
一緒に、迷いのない“気持ちの伝え方”を見つけましょう。
STEP 1:まず知っておきたい「有志一同リスト」の基本と役割

「有志一同リストって、ただ名前を書くだけでしょ?」
——そう思っていた時期が私にもありました。
でも実際に幹事役を任されてみると、「名前の順番どうする?」「金額って書くべき?」「敬称どうする?」と迷うことばかり。しかも渡す相手が目上の人だったり、香典のような弔事となればなおさら、失礼のないように気を遣いますよね。
まずは、有志一同リストが「なぜ必要なのか」「どういう役割を果たすのか」をしっかり押さえておきましょう。
🎯 有志一同リストとは?ただの名簿じゃない
有志一同リストとは、複数人で協力してお金や品物を出し合うときに、その参加者の名前や金額を記録した一覧表のこと。
代表的な場面は次の通りです:
- 退職祝い(職場での贈り物や寄せ書き)
- 結婚・出産祝い
- 香典・供花
- 記念品贈呈(卒業やプロジェクト完了など)
- 地域や学校行事での募金・カンパ
このリストは、ただ「誰が出したか」だけを記録するものではなく、気持ちを形に残す大切なツールなんです。
💬 気持ちの可視化と記憶の共有
たとえば、退職する先輩への贈り物に20人が参加したとしましょう。
「有志一同」とだけ書いてあるだけでは、もらった側も「誰が協力してくれたのかな?」と分からず終わってしまいます。でも名前のリストがあれば、「あの人も入ってくれてたんだ」と、受け取った側も心に残りやすいのです。
また、時間が経ってから「前回どうしてたっけ?」というときにも、このリストがあると振り返りやすく、記録としての価値もあります。
💰 金銭管理の透明性とトラブル防止
もうひとつの大きな役割が、お金の出入りを“見える化”すること。
「いくら集めたの?」「誰がどれだけ出した?」と後から聞かれても、リストがあれば即答できます。
特に金額がバラバラな場合は要注意。後から「私は3,000円しか出してないのに、5,000円って書いてあった」なんてトラブルにならないよう、正確で明確な記録が欠かせません。
🛡 誰のため?幹事の“自衛”にもなる
幹事という役目は、やってみると分かりますが、ものすごく気を遣うポジションです。
「私、入ってないんだけど…」「名前、間違ってるよ…」と言われないように、事前の確認や記録の残し方がとても重要。
有志一同リストは、**幹事が自分の身を守るための“盾”**でもあるのです。
✅ この章のまとめ
- 有志一同リストは、気持ちとお金を可視化する「思いやりの名簿」
- 正確な記録が、トラブル予防と信頼の土台になる
- 幹事自身の負担軽減にもつながる「備えあれば憂いなし」のツール
STEP 2:書く前にチェック!有志一同リストの基本マナー

有志一同リストを作るときに、一番怖いのは“うっかりの失礼”。
名前の順番、敬称のつけ方、金額の書き方…全部が「ちょっとしたこと」なんですが、その“ちょっとした違和感”が相手に伝わってしまうのが、こういうリストの怖いところです。
逆に言えば、ここで最低限のマナーを押さえておけば、それだけで「ちゃんとしてるな」と思ってもらえるリストになります。
📌 名前の順番にルールはある?五十音順と役職順の使い分け
まず迷うのが、名前の並べ方。
基本的なパターンは以下の2つです:
- 役職順(会社・団体の場合):目上の人 → 役職なしの人 → アルバイトなど
- 五十音順(全員同格の場合):公平感を出したいときに便利
「どっちが正しいの?」ではなく、「この場面ではどちらがふさわしいか」を考えるのが正解です。
特に職場では、上司を部下の下に記載してしまうと、ちょっとした不快感を生むこともあるので要注意。
💰 金額は一律?個別?それぞれの記載パターン
金額の記載については、大きく2通りの方法があります。
- 全員同額の場合
→ 「○○円 × 〇名 合計○○円」といったまとめ書きでOK - 金額に差がある場合
→ 各人の名前の横に金額を記載
(例:山田 太郎 3,000円)
金額の差を明記する場合は、本人の了承を得てからが基本マナーです。「え、なんで私だけ多いの?」といった気まずさを生まないよう、事前に確認しておきましょう。
🙇 敬称・字体・表記の統一で“雑さ”を防ぐ
ありがちなのが、リストの中で「様」「さん」「敬称なし」が混在してしまうケース。たとえばこんな感じ:
- 山田 太郎 様
- 佐藤 花子
- 鈴木 一郎 さん
これ、けっこう目立ちます。そして受け取った側からすると「適当に書いた?」という印象に。
敬称は「統一」が最重要です。どれを使うかより、すべて同じにすることが大切。
ちなみに、社外に見せる可能性がある場合は「様」、内輪向けなら「さん」や敬称なしでもOKです。
🌀 「様」「さん」どっちが正解?よくある表記の混乱例
「上司は“様”、同僚は“さん”でもいいのでは?」と思いがちですが、リスト内で敬称を変えると、それだけで“差をつけた感”が出てしまいます。
どうしても分けたい場合は、「上司だけ別枠にする」「役職を表記して統一する」といった構成上の工夫でカバーするのがスマート。
▼統一の例:
- 山田 太郎(部長)
- 佐藤 花子(主任)
- 鈴木 一郎(一般)
こうすれば敬称の混乱を防ぎつつ、上下関係も自然に伝わります。
✅ この章のまとめ
- 名前の並び順は、役職順 or 五十音順を状況に応じて使い分け
- 金額の記載は、全員一律か個別記載かを事前に確認
- 敬称・表記・字体は「すべて統一」が絶対ルール
- 混在を避けるために、最初にリストの“書式ルール”を決めておくと◎
STEP 3:用途別で変わる!香典・退職祝い・記念品での注意点

「有志一同リストの基本はわかった。でも、香典と退職祝いって全然雰囲気が違うよね?」
——そのとおりです。
同じ「有志一同」でも、シーンによってふさわしい書き方や配慮ポイントが大きく変わります。場違いな書き方をしてしまうと、相手に不快な印象を与えてしまうことも…。
この章では、よくある3つのケース——退職祝い、香典、記念品贈呈——について、それぞれの注意点を具体的に解説していきます。
🎉【退職祝い】平等感と感謝が伝わるリストに
退職祝いの場合は、送り出す人への感謝やねぎらいの気持ちを込めることが第一。
ポイントは以下の通りです:
- 金額は一律が基本:金額の差が出ると、渡すときの空気が気まずくなりがち。事前に「○○円で統一しましょう」と全員に伝えておくと◎。
- 贈り物の内容と金額を明記:たとえば「記念品として万年筆を贈呈、残金は花束購入に使用」といったように、お金の使い道を明記しておくと透明性が高まります。
- 部署名やグループ名の記載も有効:誰が参加しているかを相手が把握しやすくなります。
ちょっとした寄せ書きやメッセージカードを添えると、温かみがグッと増します。
🕊【香典】宗教・慣習に注意!“形式美”が命
香典リストは、最もマナーが求められるシーンのひとつ。
特に注意したいのが宗教や地域ごとの違いです。
- 表書きは「有志一同」NG?:「有志一同」と表書きするのは本来は誤りとされ、「○○課有志」や「○○一同」とするのが正式です。
- 名簿は縦書き・フルネーム・金額は漢数字で:たとえば「五千円」「壱万円」など。香典返しの際に使われるため、住所や会社名も記載するのがマナー。
- 香典返し不要の場合は、「香典返し無用」など一筆添えておくと親切です。
香典袋は宗派により違いがあるので、「仏式か?神式か?キリスト教か?」を確認してから準備しましょう。
🎁【記念品】名前だけでもOK?柔軟さが求められるケース
記念品贈呈では、金額の記載が省略されることも多いです。
たとえば、卒業記念品やプロジェクト達成時など、贈り物が主役になる場合は:
- 「営業部有志一同」とだけ書き、参加者の名前を別紙に添える
- 金額は記載せず、「気持ちの贈り物」として演出
- 手書きのメッセージや寄せ書きをプラスして、形式より気持ち重視
このケースでは「見せる」リストというより、「添える」リストという扱いに。
TPOに合わせて、温度感を調整するのがポイントです。
🏫【PTA・町内会】地域活動ならではの配慮
- 年齢や立場を尊重した並び順(年長者→若年者など)
- 金額の差が出やすい場合は、個別金額の記載を丁寧に
- 過去の記録が残っていれば、前年のリストを参考に
- 「〇年〇月〇日、〇〇イベント支援金として」など、目的を明記
地域活動では、あとで「あの人入ってたっけ?」という確認にもリストが役立ちます。
✅ この章のまとめ
- 退職祝い:全員一律+使い道明記で信頼度UP
- 香典:宗教に応じた書き方が必須。表書きや名簿形式に要注意
- 記念品:金額省略もOK。名前+メッセージで気持ち重視
- PTA・町内会:年齢順や記載の丁寧さで“地域の礼儀”を表す
STEP 4:実例でわかる!用途別テンプレート集

「で、結局どう書けばいいの?」
そんな声にお応えして、この章ではそのまま使えるテンプレートをシーン別に紹介します。
実際の文面やレイアウトを見ながら進めることで、「これならすぐ作れる!」とイメージが湧くはず。印刷して使ってもよし、Googleスプレッドシートなどにコピペしてもよし。ぜひご活用ください。
🎉【退職祝い用テンプレート】温かく、でもスマートに
有志一同リスト(退職祝い)
令和〇年〇月〇日
氏名 金額
山田 太郎 3,000円
佐藤 花子 3,000円
鈴木 一郎 3,000円
合計金額:9,000円
※記念品代として〇〇〇を購入し、残金〇〇〇円は花束代に使用しました。
💡ポイント
- 金額は一律で揃えるとスッキリ
- お金の使い道を明記すると透明性UP
- 必要に応じて部署名を併記しても◎
🕊【香典用テンプレート】格式重視の正式版
有志名簿(香典)
令和〇年〇月〇日
会社名:株式会社〇〇
住所:〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
氏名 住所 金額
田中 正 〒000-0001 東京市A区B町1-1 五千円
中村 洋子 〒000-0002 東京市C区D町2-2 五千円
高橋 健 〒000-0003 東京市E区F町3-3 三千円
合計金額:一万三千円
💡ポイント
- 縦書き推奨(印刷時は縦書きフォーマットに変換を)
- 金額は漢数字で「五千円」「壱万円」など
- 住所・会社名を記入するのがマナー
- 香典返し辞退の場合は「香典返し無用」と一言添える
🎁【記念品贈呈用テンプレート】自由度の高い“添え書き”
有志一同(記念品贈呈)
令和〇年〇月〇日
参加者一覧(〇〇部)
山本 健、松井 優、伊藤 真、佐藤 知美
※この記念品は〇〇プロジェクト完了を記念して、上記有志により贈呈いたします。
💡ポイント
- 金額記載は不要。品物が主役
- メッセージを加えると気持ちが伝わる
- 誰が参加したかを簡潔に表現
🛠【ちょっと便利なテンプレ活用の工夫】
- ExcelやGoogleスプレッドシートで作成
→ リアルタイムで編集・共有が可能 - PDFで保存&印刷
→ フォントの乱れや印字ズレ防止に最適 - クラウド保存で再利用
→ 次回のイベントでもすぐ再利用できる!
✅ この章のまとめ
- テンプレは用途ごとにマナーが異なるため、コピペで使う前に内容確認を
- フォーマットは整えることで“ちゃんとしてる感”が出せる
- オンラインツールと組み合わせることで効率化&ミス防止
STEP 5:トラブル回避!作成時にありがちなミスと解決法

有志一同リストで起きるトラブルの多くは、「悪気はないけど…」の“うっかり”から発生します。
でも、たった1つの名前のミスが、「私は参加したのに名前が載ってない」「字が違ってて気分悪い」なんてことにも。些細なズレが、あとあと尾を引くのがこの手の“名簿トラブル”の怖さです。
だからこそ、よくあるミスをあらかじめ知っておくことが、幹事の最大の防衛策になります。
❌ ミス1:名前の誤字脱字 → “信用”に関わる最重要ポイント
リスト作成で最も多いミスが人名の漢字間違い。
例:
- 「渡辺」を「渡邊」に
- 「高橋」を「髙橋」に
- 「斉藤」を「齊藤」「斎藤」「斉藤」で混乱
名前はその人にとって最も大事なアイデンティティ。1文字違うだけで「自分を雑に扱われた」と感じる人も。
📌解決策
- 名簿提出時に本人確認を必ず取る
- 社内メールやチャット履歴から正式表記をコピーする
- フォントの変換で「髙」「﨑」などの旧字もチェック
❌ ミス2:金額の記入ミス・記載漏れ → 不信感の元に
「自分は5,000円出したはずなのに、リストには3,000円と書いてある…」
このような金額の間違いは、一瞬で信頼を損なう大問題。
📌解決策
- 金額記録はスプレッドシートでリアルタイム管理
- 入金時点で金額と名前をセットで記録する
- リスト提出前に全員に確認してもらう
❌ ミス3:「誰を入れる・外す?」で気まずい空気に
「あの人も参加したかったのに声がかかってなかった」
「なんであの人だけ入ってるの?」
こういった参加者選定ミスは、トラブルというより“空気が悪くなる”系のやっかいな問題です。
📌解決策
- 初めに「対象はこのグループの人だけです」と明確に周知
- あいまいな立場の人には「ご希望あれば追加します」と伝える
- “巻き込みすぎない”のも大人のマナー
❌ ミス4:香典返しで困る → 名簿不備が後々に響く
香典返しの際に必要なのが「誰から、いくら」という正確な情報。
香典リストを省略してしまうと、遺族側で混乱が起きる原因に。
📌解決策
- 住所・氏名・金額をきちんと記載
- 香典返し不要の場合も「お返し無用」の一筆を添える
- 宗教形式(仏式・神式など)に合った書式か再確認
✅ この章のまとめ
- 名前の表記ミスは最も避けるべき重大トラブル
- 金額の誤記・漏れは信頼を一気に崩す
- 誰を入れるか・外すかの線引きは、あらかじめ共有しておく
- 香典リストの不備は、喪家側に迷惑をかける可能性大
STEP 6:オンラインで効率UP!リスト作成の便利ツール活用法

「人が多くて全員の名前と金額を手作業で集めるのは無理ゲー…」
「確認作業が何度も往復して、もう疲れた…」
そんな幹事さんのために、今や**“手書き時代”から“オンライン時代”へ**。
無料で使えるツールをうまく活用することで、リスト作成の手間・漏れ・ストレスを劇的に減らせます。
この章では、スプレッドシートやフォーム、PDF化までの活用術をご紹介します。
🗂 Googleスプレッドシートでリアルタイム共同作業
- 複数人が同時に編集できる
- 履歴が残るので「誰がいつ書いたか」がわかる
- スマホからも編集OK
テンプレートとして使える基本構成:
| 氏名 | 金額 | 敬称 | 部署 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | 3,000円 | 様 | 営業部 | 寄せ書き希望 |
📌ポイント
- 事前に「この列に入力してください」と見本を作っておく
- 編集者にアクセス権限を限定して、誤操作を防止
📮 Googleフォームで情報収集を一元化
「いちいち聞きに行くのが大変…」そんなときはGoogleフォームが便利!
- 氏名、金額、参加の有無などをアンケート形式で回収
- 回答内容がそのままスプレッドシートに反映される
- 「未提出者リスト」も自動で作れる
📌ポイント
- 回答期限を設けておくとダラダラしない
- プライバシーに配慮して、個別通知&入力方式がベター
📄 最終版はPDFにして“きちんと感”を演出
デジタルで管理していても、提出時は紙 or PDFが基本。
特に以下のような場面では、印刷 or PDF保存が効果的です:
- 会社の上司に確認をもらうとき
- 香典返しなど、相手方に渡すとき
- 記録として保管したいとき
📌ポイント
- フォントを統一して読みやすく(明朝体やゴシックなど)
- 印刷前にレイアウトを整える(余白・改行チェック)
☁️ クラウド保存で「次回も使える」資産に
- GoogleドライブやDropboxで安全に保管
- 「〇〇さんの結婚祝いリスト」など、名前+日付で管理
- 引き継ぎ時にも便利!
🔁イベントが多い組織では、過去のリストがそのままテンプレになることも。経験値を“資産化”するのが、できる幹事の秘訣です。
✅ この章のまとめ
- スプレッドシートでの共同編集が作業効率を最大化
- Googleフォームで情報収集をスマートに
- 提出用にはPDFで「ちゃんとしてる感」を演出
- クラウド保存で“次回も困らない”準備を
STEP 7:その後も安心!保存・共有・引き継ぎのコツ

無事にリストを作って贈り物や香典を渡し終えた瞬間、幹事としては「やっと終わった…!」とホッとしますよね。でも、ここで終わらせないのが“できる幹事”の一歩先行く気配りです。
この章では、後日の共有・保存・引き継ぎに関するちょっとしたコツをまとめました。
🗂 「何のために作ったか」を明記して保存
有志一同リストは、後で「これは何のリストだっけ?」と迷われることが多いもの。日付と目的を書き添えておくだけで、未来の自分や後任へのメッセージになります。
📌保存ファイル名の例:
【退職祝い】山田部長_有志一同リスト_2025年3月
【香典】佐藤様ご逝去_香典名簿_2025年6月
👥 必要な人にだけ共有するのが大人のマナー
「上司や会計係には共有したいけど、全員に見せるのはちょっと…」
そんなときは限定共有が安心。
GoogleドライブやDropboxなら、共有リンクに閲覧権限を設定できます。
💡注意点:
- 金額や個人情報が含まれるため、全体共有は避けるのが無難
- 場合によってはパスワード付きZIPファイルで渡すとより丁寧
🔁 引き継ぎのために「まとめノート」を残しておく
幹事をやってみて初めてわかる、あの面倒くささ。
次に担当する人が同じ思いをしないように、サクッと以下の情報を残しておくと喜ばれます:
- 使用テンプレート(ExcelやPDF)
- どんな方法で集金・確認をしたか
- 注意点(誤字注意・金額記録方法など)
💡ヒント:
Googleドキュメントやメモアプリで簡単な「引き継ぎメモ」を作っておくと、後任の神になります。
📚 アーカイブは“経験の資産化”
イベントが繰り返される会社や団体では、過去のリストがそのまま見本や判断材料になることも。
- 「去年は誰がどれくらい出したか?」
- 「前任者はどうまとめたか?」
- 「あの時、誰が参加してたか?」
こうした情報を残しておくことで、次回以降の負担が激減します。
特に香典など、突然必要になるものほど、事前の備えが役立つものです。
✅ この章のまとめ
- ファイル名と目的を明確にして“迷子防止”
- 共有範囲は最小限に。個人情報は丁寧に扱う
- 引き継ぎメモで次の幹事の救世主に
- リストはただの記録ではなく、“未来への資産”になる
記事全体の総括

有志一同リストは、ただの「名簿」でも「金銭記録」でもありません。
それは、**人と人との思いやりをつなぐ“記録以上の記録”**です。
退職祝いで「ありがとう」の気持ちを形にしたり、香典で「お悔やみ」と「敬意」を丁寧に伝えたり、記念品で「一緒にがんばったね」という連帯感を残したり——そのすべてにリストは静かに寄り添っています。
今回ご紹介したように、名前の順番ひとつ、敬称の統一ひとつで、印象は大きく変わります。
シーンごとのマナーや記載例を正しく押さえ、気持ちよく、失礼のない対応ができれば、それはきっと周囲からの信頼や評価にもつながっていくはずです。
幹事や代表に任命されるということは、それだけ“人望”があるということ。
だからこそ、その役目を丁寧に全うし、受け取る人にも、参加する人にも、「やってくれてありがとう」と言ってもらえるようなリストを作りましょう。
忙しい毎日の中でも、少しの工夫と準備で、想いの伝わり方は確実に変わります。
あなたが手間をかけて作るそのリストは、誰かの心にちゃんと届く贈り物になります。
形式にとらわれすぎず、けれど丁寧に。
「またお願いしたい」と思われるような、“気配りのある人”としてのあなたの姿勢が、きっと次のチャンスを呼び込んでくれるはずです。
どうかこのガイドが、そんな未来への一歩になれば幸いです。