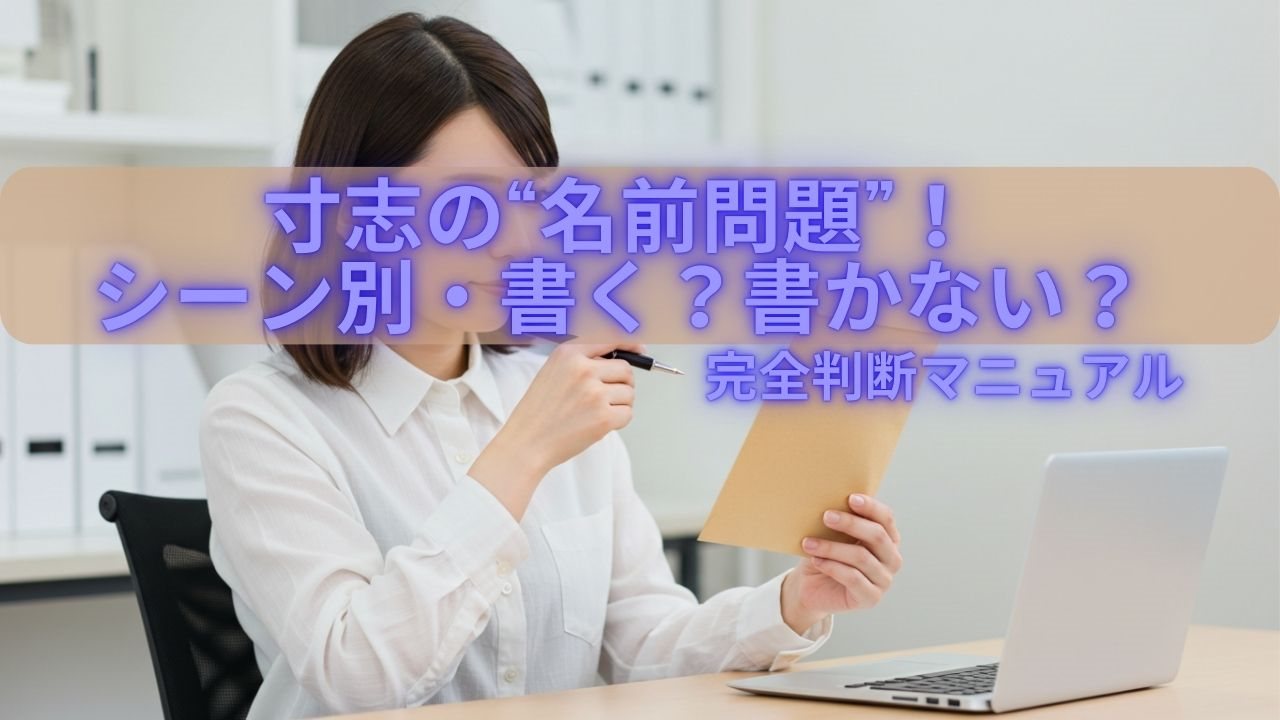「名前を書かなくても、マナー違反ではありません——ただし“場面によります”。」
寸志を包むとき、「これって名前、書くべき?書かないべき?」と戸惑った経験はありませんか?
社内イベントや送別会、地域行事や葬儀など…寸志を渡す場面は多いのに、意外と正解が見つからない。
しかも、誰かに聞こうにも「今さら聞けない」空気。だからこそ多くの人が、“間違えたくない”けど“自信がない”という不安を抱えています。
本記事では、そうしたお悩みに対して、「どのシーンで、名前を書くべきか・書かなくてもよいか」を具体的かつ実践的に整理しました。
さらに、封筒の書き方や渡し方、表書きの選び方まで、社会人として恥をかかないためのマナーを網羅しています。
この記事を読めば、もう寸志の“名前問題”で迷うことはありません。
むしろ、さりげなくスマートに渡せることで、あなたの気遣いと信頼感がぐっと高まるはずです。
🖋 第1章:まず知っておきたい!寸志の基本と“名前の書き方”が問題になる理由

寸志とは何なのか、なぜ「名前を書く・書かない」で迷いが生まれるのか。その背景を知らないままだと、形式だけをなぞって“なんとなく”で済ませてしまいがちです。
まずは、寸志という文化の基本と、名前の取り扱いにまつわる考え方から整理してみましょう。
寸志ってそもそも何?「気持ちを包む」文化の背景
「寸志(すんし)」という言葉、よく耳にはするけれど、いざ自分が使うとなると「正しくわかってる?」と自信がなくなる人は多いかもしれません。
寸志とは、読んで字のごとく「ほんの少しの心遣い」という意味合いを持つ言葉です。金額の多寡よりも、「ありがとう」「おつかれさま」の気持ちを形にしたもの。ボーナスのように制度化されたものではなく、もっとカジュアルで、あたたかみのある贈り物です。
たとえば、忘年会の幹事へのねぎらいや、送別会の主催者への感謝、あるいは結婚式の受付を引き受けてくれた友人への心ばかりの謝礼…。そういった場面で「これ、少しだけど…」と手渡す寸志には、お金以上の気持ちが詰まっています。
こうした「気持ちを包む」日本独自の文化は、時に形式やマナーとして厳しくも映りますが、その根底には「相手を大切に思う」やわらかな気配りが流れています。
なぜ「名前を書く・書かない」が気になるのか
さて、本題です。寸志を渡すとなったとき、封筒には何を書けばいいのでしょうか?
「寸志」と書くのは分かるとして、その下に自分の名前は書くのか、書かないのか。
これ、実は多くの人がつまずくポイントです。
しかも、どのマナー本を読んでも「場合による」と書かれていて、「結局どうすればいいの?」と迷ってしまうのが現実。
名前を書くかどうかは、シーンによって“正解”が変わるというのが、ややこしさの原因です。
たとえば、
- 社内イベントでは「名前を書かない方がスマート」
- 個人への謝礼では「名前を書かないと失礼」
- 葬儀では「必ず名前を書く」
- 地域の集まりでは「先例を確認するのがベスト」
といった具合に、「TPOに応じた対応」が求められます。
この名前問題、なぜそこまで神経質になる必要があるのかというと、それは**“寸志=気持ち”だからこそ、「誰の気持ちか」が重要になる場面がある**からです。
一方で、「目立たないように贈ることが粋」とされる場もあり…
うっかり名前を書いたことで“恩着せがましい”と受け取られてしまうケースもゼロではありません。
つまり、「名前を書くか否か」は、受け手への敬意と空気を読む力が試される、微妙なマナーのひとつなのです。
知らずに恥をかく?“名前問題”でありがちな失敗例
たとえば、こんな話があります。
とある新入社員が、忘年会の最後に幹事への寸志を封筒に入れて渡しました。丁寧に筆ペンで自分の名前も記し、心を込めて手渡したのですが、その封筒を見た幹事の先輩が少し困惑した様子。
「ありがたいけど…こういうのって、名前は書かないのが普通なんだよね。逆に気を使わせちゃうから…」
本人は良かれと思ってやった行動が、かえって気まずさを生んでしまったのです。
逆に、こんなケースも。
町内会の行事でお手伝いをしてくれた年配の方に寸志を渡したが、名前を書いていなかったため、「これは誰から?」「会費?謝礼?何?」と混乱が起きてしまった…。
こうした行き違いを防ぐには、事前の判断軸を持っておくことが大切。
「この場では名前を書いたほうが丁寧だろうか?」「空気を読んで控えめにすべきだろうか?」という視点があるだけで、寸志はもっとスマートに、好印象で渡せるものになるのです。
✅この章のまとめ
- 寸志とは「少額でも感謝を伝える」文化的なマナー
- 名前を書くか書かないかは、場面ごとに“正解”が異なる
- うっかりの判断ミスで、気まずさや誤解を招くことも
- 「気持ちを伝える」ための最善の方法は、空気を読むこと!
🖋 第2章:【基本ルール】のし袋・中袋の書き方と「名前の書き方」黄金パターン

寸志を包む際に避けて通れないのが、封筒や中袋の正しい使い方。表書きは?
名前はどこに?
何で書けばいい?…そんな疑問を解消するために、基本ルールを押さえておきましょう。
ここでは、シンプルで失敗しない書き方のコツをご紹介します。
表書きは「寸志」or「御礼」?場面別に最適解
寸志を包むとき、まず迷うのが「のし袋の表書きに何と書くべきか?」ということ。
「寸志」って書けば全部OKでしょ?——いえいえ、実はシーンによって“最適な表現”が異なるのです。
たとえば…
- 社内イベント(忘年会・歓送迎会): → 表書きは「寸志」でOK(控えめな謙譲表現)
- 個人的な謝礼(手伝いのお礼など): → 「御礼」または「謝礼」が丁寧
- 葬儀などの弔事での心づけ: → 「寸志」「御礼」も使えるが、水引と組み合わせに注意
- 取引先・目上の方へ: →「薄謝」「松の葉」といった言葉の方が好印象なケースも
つまり、「寸志」はあくまで謙譲表現。「自分より目上の人に感謝の気持ちを表す」ための言葉なのです。
一方で、「御礼」は誰にでも使える万能表現。迷ったら「御礼」で無難に収まります。
裏面に名前を書くのはいつ?“中央下部”のルール
のし袋の裏面、意外と見落とされがちですが、ここにもマナーが詰まっています。
基本的なルールはこうです:
- 縦書きで中央下部にフルネームを書く
- 使用するのは筆ペン、または黒インクの万年筆
- サインペンやボールペンは避ける(カジュアルすぎる印象に)
ただし、すべてのケースで「名前を書くべき」わけではありません。
📌 名前を書くべき場面
- 感謝を明確に伝える個人宛の謝礼
- 葬儀・弔事での寸志(誰からかを管理する必要があるため)
- 町内会など公的な行事での寸志
📌 名前を書かない方がいい場面
- 社内イベントなどで主催者に渡すとき(あえて個人を強調しないのがマナー)
- 上司や先輩に渡すとき(恩着せがましくならないように)
⚠️ どうしても迷ったときは、「中袋にだけ名前を書く」「小さなメモを同封する」といった方法も有効です。
中袋があるとき・ないときのスマートな書き方
封筒には、表の「のし袋」と、中にもう一枚「中袋」が付いていることがあります。
この中袋の扱いも、意外と見落とされがちです。
【中袋ありの場合】
- 表面中央に「金 壱千円」など、旧字体を使って金額を書く
(例:壱・弐・参・伍・拾・萬 など) - 裏面の左下に、住所と氏名を書く
✅ 書き方例(中袋)
【表面】 金 参千円
【裏面】 東京都〇〇区△△1-2-3 山田 太郎
【中袋なしの場合】
- 現金はそのままのし袋に入れてOK
- ただし、白い紙で丁寧に包むと気配りが伝わる
- 名前と金額は、小さなメモに書いて一緒に入れると親切
こういった「ちょっとした一手間」が、受け取る側の印象をぐっと良くしてくれます。
書く道具にもマナーがある?筆ペン・ボールペン問題
「字に自信がないから…」とボールペンでササッと書いてしまうのはNG!
正式なマナーでは、毛筆または筆ペンの黒インクが推奨されています。
理由は簡単、「改まった場」にふさわしい“格”が出るからです。
とはいえ、筆ペンに慣れていない人も多いので、以下のような対策もおすすめ:
- 100円ショップで売っている練習用封筒を活用
- 予備の封筒を必ず数枚用意しておく(失敗しても焦らない)
- どうしても筆ペンが苦手なら、黒インクの万年筆や濃いサインペン(毛筆風)でも代用可能
ポイントは、「ていねいに書かれた感じがあるかどうか」。
字が下手でも、“雑に見えない”ことが最優先です。
✅この章のまとめ
- 表書きの言葉はシーン別に選ぶ!「寸志」「御礼」「松の葉」など使い分けが重要
- 名前を書く位置は“裏面中央下部”が基本。ただし書かない方が良い場面もある
- 中袋には金額・名前・住所を記載。旧字体を使うとより丁寧
- 道具選びも“気遣い”の一部。筆ペン推奨、ボールペンは避けよう
🖋 第3章:【シーン別マニュアル】名前を書く?書かない?迷いがちなケース全対応

社内イベントから葬儀、町内会まで、寸志を渡す場面は実にさまざま。
そのとき、最も多くの人がつまずくのが——
「この場面、名前って書くべき?それとも書かないほうがいい?」という判断。
この章では、よくあるシチュエーションを徹底的に分解して、「書く」「書かない」の実践的な判断基準を深掘ります。
場面ごとの正解を明快に整理しながら、“恥をかかない寸志の名前判断”を具体的に解説します。
✅ 社内イベント(忘年会・歓送迎会・社員旅行など):名前は“書かない”のがスマート
社内イベントで幹事や主催者に寸志を渡す場合、名前はあえて書かないのが一般的です。
なぜなら、
- 寸志=あくまで“気持ち”としての贈り物
- 個人名を強調しないほうが、かえって「スマートな配慮」として受け取られる
- 特に上司が部下に渡す場合は、「自分の名前を表に出さない謙虚さ」が好印象
表書きは「寸志」、封筒は白封筒や水引のない無地のものが適しています。
🔹 ワンポイント:
中袋がある場合は、そちらにのみ名前を記載しておくと受け取り側が混乱しません。幹事が複数人いる場合にも便利です。
✅ お礼(仕事の手伝いやサポートへの謝礼):名前は“必ず書く”べし
たとえば、同僚が急な残業を代わってくれた。
あるいは、社外の取引先が資料作成を手伝ってくれた——
そんなときの「お礼寸志」では、名前をきちんと書くのがマナーの基本です。
理由はシンプル。
「誰からのものか分からない」= ちゃんと感謝が伝わらない
特に相手が社外の人や目上の方であればあるほど、名前なしは失礼にあたる可能性があります。
🔹 書き方例:
- 表書き:「御礼」または「寸志」
- 封筒の下段中央にフルネームを縦書き
- 中袋があれば、そちらにも名前・金額を明記
気持ちを丁寧に伝えるには、「自分の名前を添える」ことが最初の一歩なのです。
✅ 葬儀・火葬場職員などへの寸志(香典代わり):名前なしは“絶対NG”
弔事関係の寸志では、名前を書かないのは大きなマナー違反です。
火葬場や霊園の職員への謝礼(寸志)は、実質的に「香典代わり」として扱われることもあり、
「誰から」「どれだけの寸志があったか」が記録・管理される必要があります。
このため、封筒の表にも裏にも、名前を明記するのが基本です。
🔹 書き方ポイント:
- 表書き:「寸志」または「御礼」
- 水引:黒白または双銀の結び切り
- 名前は封筒の下段に縦書きでフルネーム
- 中袋にも名前・住所・金額を記載(旧字体推奨)
※ただし、薄墨で書く必要はありません。通常の黒インクでOKです。
✅ 町内会・自治会行事:ケースバイケースだが「書く」が基本
地域行事でのお手伝いや協力者への寸志の場合、名前を書くほうが無難です。
理由は、
- 公的な行事の一環として渡されるため、記録や管理の必要がある
- 誰が何を出したか不明になると、会計処理やお返しの際にトラブルになることも
ただし、地域の慣例によっては「書かない文化」のところも存在します。
このため、「前回どうだったか?」「他の人はどうしているか?」を先に確認するのがベストです。
🔹 安心パターン:
- 表書き:「寸志」または「謝礼」
- 名前は封筒の下段に縦書きでフルネーム
- 中袋には金額と住所も記載しておくと親切
✅ 団体名で出すときは?:「〇〇部一同」「〇〇会社〇〇課」で統一
職場やPTAなどで連名ではなく団体名で寸志を出すこともよくあります。
この場合は、個人名ではなく団体名を裏面中央下部に記載するのが正解です。
🔹 記入例:
- 表書き:「寸志」
- 裏書き:「営業部一同」「〇〇株式会社 総務部」など
中袋に金額を明記し、個人の名前は省略してOK。
ただし、代表者が渡す場合は、「〇〇部を代表して」と口頭で伝える配慮を。
✅ 表で名前を書かずに“中袋だけ”に記名するテクニック
ちょっとしたTIPSですが、「名前を表に出したくないけど、誰からかわかってほしい」という微妙な場面では…
中袋にだけ名前を書くのが、さりげなく気持ちを伝えるベストな手段です。
これにより、表面は控えめな印象に、
中身ではしっかり“誰からの寸志か”が伝わります。
✅ 早見表:シーン別・名前の記載判断まとめ
| シーン | 名前の記載 | 備考 |
|---|---|---|
| 社内イベント | × 書かない | 控えめがマナー。中袋に書くのは◎ |
| お礼・謝礼(個人) | ○ 書く | 感謝を明確に伝える |
| 葬儀・火葬場関係 | ○ 書く | 管理・記録が必要。不記名はNG |
| 町内会・地域イベント | △ 要確認 | 地域差あり。迷ったら「書く」が安心 |
| 団体名での贈答 | ○ 書く | 個人名は書かず、「一同」「会社名」などで統一 |
✅この章のまとめ
- 寸志の名前は「書く・書かない」でマナーが変わる
- 社内イベントは“書かない”が基本、お礼や葬儀は“書く”がマナー
- 地域行事は「前例」を確認し、迷ったら“書く”方を選ぶと安心
- 団体名の場合は、裏面に団体名だけでOK
🖋 第4章:こんなとき要注意!“書かない”ことでマナー違反になる例と対処法

「名前を書かない方がいいと聞いたから…」
「気を使わせたくないし、匿名で渡そう」
——その判断、本当に正しかったのでしょうか?
「控えめにしたつもりが失礼に見えた」
「名前がないことで困惑された」——そんな意図しないミスは、寸志では意外と起こりやすいもの。
この章では、“名前を書かない”ことで思わぬ誤解やトラブルを招いたケースをもとに、マナー違反にならないための対処法を具体的に解説していきます。
❌ ケース1:「誰から?」と相手が混乱してしまった…
町内会のイベントで、役員のひとりが寸志をまとめて用意し、スタッフに配ったときのこと。
封筒の表には「謝礼」とだけ書かれていて、誰の名前も書いていない。
受け取った側は「これは町内会費から?」「個人のお礼?」と判断がつかず、受け取ってよいものかどうか戸惑ってしまいました。
🔍 ここが問題:
- 名前がないことで**「誰からのものか」が曖昧**
- 特に複数人から同時に渡される場では、管理ができずトラブルのもとに
✅ 対処法:
- 表に名前を書きたくない場合は、中袋にだけ記名
- 口頭で「これは〇〇会からの寸志です」と一言添える
❌ ケース2:「恩着せがましい」と思われてしまった…
ある若手社員が、歓送迎会で幹事に寸志を渡す際、筆ペンでしっかり自分の名前を書いて封筒を手渡し。
その場では丁寧な印象でしたが、後になって「自己主張が強い」「何か狙ってるのでは?」と裏で陰口を言われてしまいました…。
🔍 ここが問題:
- 社内イベントでは「個人の名前を目立たせること」が逆効果になることも
- 上司から部下へなら問題ないが、横並びの立場だと微妙
✅ 対処法:
- 名前は中袋や内メモにとどめる
- 表面はあくまで「寸志」などの簡潔な表現にする
- 渡すときにひと言で誠意を補足する:「ほんの気持ちです。皆さんでお使いください」
❌ ケース3:「名前がない=誰にも感謝されていない」と誤解された…
退職する同僚に、部署一同で寸志を渡したときのこと。
封筒の表には「御礼」、裏には「営業部一同」とだけ書かれていたのですが…
後日、その同僚がポツリとこんなことを言ったのです。
「結局、誰も個人で何も言ってくれなかったな…寂しいもんだね」
本当は皆で感謝の気持ちを込めて用意した寸志だったのに、「誰からの言葉もなかった」ように感じさせてしまったのです。
🔍 ここが問題:
- 名前がないことで、“気持ちの主語”がぼやけてしまった
- 封筒だけ渡すと、事務的な印象になりやすい
✅ 対処法:
- 代表者が一言で気持ちを代弁する:「皆で感謝してます。これ、みんなからの気持ちです」
- 手書きの寄せ書きカードを添えると温かみUP
✅ どうしても名前を書きたくないときの“ひと工夫”
それでも、「あえて名前は出したくない」「場にそぐわない気がする」ということもあるでしょう。
そんなときにおすすめなのが、以下の方法です。
① 中袋だけに名前を書く
表面はシンプルに「寸志」、中袋にのみ名前・金額を明記。
受け取った側は、あとからこっそり確認できるため、控えめながら誠実な印象に。
② 小さなメモやカードを同封する
便箋サイズの紙に「山田より、ささやかですが感謝の気持ちです」などと一筆書くだけで、“誰から”の心遣いかが明確になります。
③ 渡すときの言葉に“名前の代わり”を込める
「いつもありがとうございます。名前は伏せていますが、気持ちを受け取ってもらえたら嬉しいです。」
このような“言葉の配慮”で、形式にとらわれすぎない柔らかさを演出できます。
✅ 名前の有無で困ったときのチェックポイント
最後に、「名前、書くべきかな?」と迷ったときに使える判断フローをご紹介します。
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 相手に「誰からか」が必要? | 書く | 書かないOK |
| 相手が目上?または社外の人? | 書く | 書かないOK |
| 社内イベントで幹事に渡す? | 書かない | 書く |
| 公的イベントや記録が必要な場面? | 書く | 書かないOK |
| 名前を出すと目立ちすぎると感じる? | 中袋に書く | 表に書く |
✅この章のまとめ
- 名前を書かないと「誰から?」と不信感を招くことがある
- 社内では目立ちすぎないよう注意。相手との関係性を重視しよう
- “書かないけど伝える”テクニックで、誠実さと控えめさのバランスを取る
- 困ったときは、「中袋だけ記名」「ひと言メモ」「渡し方の工夫」でカバー
🖋 第5章:表書きの言葉、どう選ぶ?「寸志」「御礼」「松の葉」などの使い分け
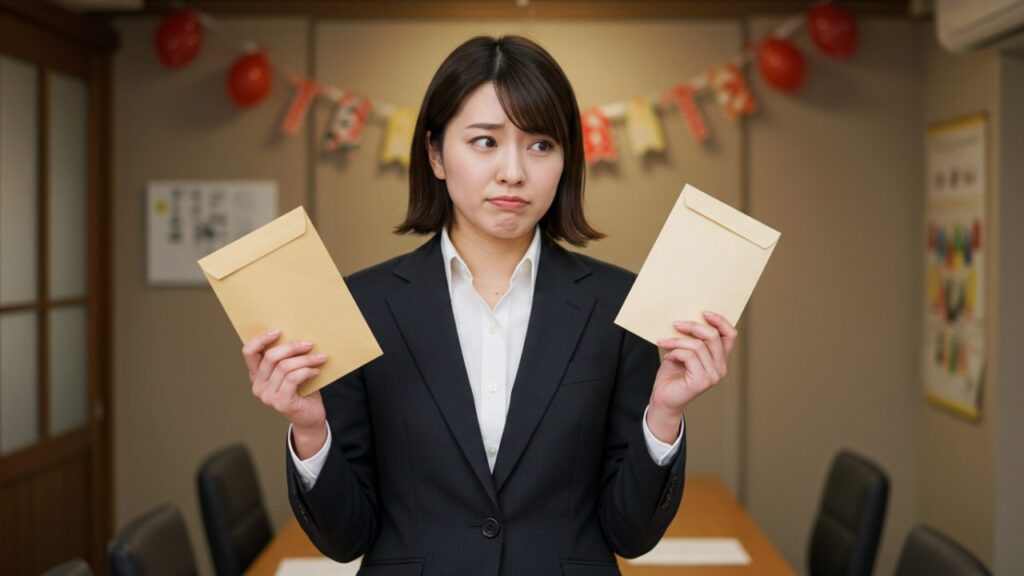
寸志を包むとき、封筒の“表書き”に何と書くか——
実はここ、名前以上にセンスが問われるポイントかもしれません。
「寸志」「御礼」「謝礼」「薄謝」「松の葉」…
言葉ひとつで相手への印象が大きく変わるからこそ、TPOに応じた使い分けが大切です。
実例を交えてわかりやすく紹介します。
「寸志」は“目上への控えめな気遣い”を伝える言葉
「寸志(すんし)」は、もっともよく使われる表書きのひとつ。
語源としては、「ほんの少しばかりの志」という意味で、
自分より“目上の人”に対して、へりくだって贈る場合に使う表現です。
そのため…
📌「寸志」を使うべきシーン
- 上司・先輩に感謝の気持ちを伝えたいとき
- 社内イベントで部下に寸志を渡すとき
- 弔事における火葬場職員などへのお礼(形式的に寸志と表す)
⚠️「寸志」は目下の人には使わないのが原則です!
たとえば後輩や部下、子どもに対しては「御礼」や「心付け」を使うほうが自然です。
「御礼」は万能タイプ!迷ったらこれでOK
「御礼」はどんな相手にも使える、マルチプレイヤー表現。
- 社内・社外どちらでもOK
- 上下関係を気にせず使える
- 「寸志」よりもフォーマル色がやや弱く、柔らかい印象
📌「御礼」が合うシーン
- 社外の人に対する謝礼(手伝いやアドバイスのお礼など)
- 同僚・後輩への感謝の寸志
- 町内会やPTAでのお手伝いへの謝意
⚠️ただし、若干“事務的”に見えることもあるので、
感情を込めたい場面では、手書きの一言や一筆箋を添えると印象がアップします。
「松の葉」ってなに?送別会や弔事で使える“やわらか敬語”
聞きなれないかもしれませんが、「松の葉」という表書きもあります。
これは、送別会などで目上の人に寸志を渡すときの、非常に丁寧な表現です。
なぜ「松の葉」か?
松は常緑で枯れない、縁起の良い植物。
つまり、「ささやかだけど、長く続く感謝の気持ち」を表す言葉なんです。
📌「松の葉」が活きる場面
- 退職する上司への送別の心ばかり
- フォーマルな場で、現金を直接渡すことに抵抗がある場合
⚠️ 注意点:若い世代や一部地域では馴染みがなく、逆に「何これ?」と戸惑われることもあります。
「寸志だと角が立つかも…でも『御礼』じゃ味気ない」
そんな場面で、“やわらか敬語”として使えるのが「松の葉」です。
「薄謝」や「謝辞」…フォーマルシーンで差がつく表現
よりビジネス寄り、もしくは格式を求められる場では、
「薄謝」や「謝辞」といった表現も視野に入れてみましょう。
✅「薄謝」= 控えめに感謝を伝える表現
- 「少額ですが…」というニュアンスを含む
- 取引先や外注先など、ビジネスの場での寸志に向いている
- 金額より気持ちを重視していることが伝わる
✅「謝辞」= 文章的なフォーマル表現
- スピーチや式典などでの“感謝の言葉”として適切
- 封筒表書きに使うケースは少ないが、ビジネス文書や案内文に強い
使いすぎると堅苦しくなりがちなので、あくまで「ここぞ」の場面で活用するのがおすすめです。
📊 使い分け早見表(相手・シーン別)
| 表書き | 意味 | 使う相手・場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 寸志 | 控えめな贈り物(謙譲表現) | 上司、先輩、社内イベントなど | 目下の人には使わない |
| 御礼 | 感謝の気持ち | 社内外の誰にでも使える | 若干フォーマル感に欠ける場合も |
| 松の葉 | 丁寧な感謝の表現(やわらか表現) | 上司の送別会、フォーマルな場 | 若い人には伝わらないことも |
| 薄謝 | 控えめな謝礼 | 取引先、外注先、金銭を強調したくない場面 | カジュアルな場には向かない |
| 謝辞 | 感謝の言葉(文章的) | 式典や公式な挨拶文など | 封筒の表書きにはやや硬すぎる |
✅ 一番大事なのは、「言葉に心があるかどうか」
どんなに正しい言葉を選んでも、そこに心が乗っていなければ、ただの形式。
逆に、多少の間違いがあっても、「ありがとう」の気持ちが伝われば、それが一番のマナーです。
だからこそ、迷ったときは——
「相手は、この表現をどう受け取るだろう?」
と考えて選ぶことが、もっとも誠実な“マナーの本質”なのです。
✅この章のまとめ
- 「寸志」は目上への控えめな感謝、「御礼」は誰にでも使える万能表現
- 「松の葉」は丁寧かつやわらかい印象、送別会や弔事におすすめ
- 「薄謝」「謝辞」はフォーマルな場での寸志に効果的
- 表書きは“正しさ”よりも、“相手への配慮と心遣い”が伝わることが大切
🖋 第6章:もらって気持ちいい寸志の渡し方:タイミング・姿勢・ひと言添え方術

寸志は、どんなに封筒や表書きが完璧でも——
“渡し方”ひとつで印象がガラッと変わるものです。
せっかくの感謝の気持ちも、無言や雑な所作では台無しに…。
逆に言えば、たとえ筆ペンの字がちょっと下手でも、渡し方が丁寧であれば相手の心に届きます。
この章では、「気持ちのいい寸志の渡し方」をタイミング・所作・声かけの3方向から解説していきます。
そして好印象を残すひと言のコツを、実践的な例とともにお届けします。
⏰ 寸志を渡すベストなタイミングは「始まる前」or「終わったあと」
「いつ渡すのが正解?」という疑問、実はとても重要です。
寸志は“場の空気”に乗って渡すもの。タイミングを間違えると、ありがたみが薄れてしまいます。
✅ ベストなタイミング:
- 会やイベントが始まる前の落ち着いたとき
- または、終了後のお礼のタイミング
📌 NGタイミング例:
- 乾杯の直後など、全員が注目している場面
- 飲み会の盛り上がりの最中(酔って忘れられる可能性大)
- 相手が忙しく動き回っているとき(幹事など)
ワンポイント:
あえて“人目につかない静かなタイミング”を選ぶのが粋。
🤝 渡すときの姿勢としぐさ:手元から伝わる「気遣い」
封筒をただ渡すだけではなく、所作(しぐさ)も立派なメッセージです。
📌 基本の所作:
- 封筒は両手で持ち、表面を相手に向けて渡す
- 渡すときは軽くお辞儀をする(深すぎなくてOK)
- 相手の手に触れないよう、そっと手元に置くのもあり
📌 封筒の扱い注意:
- くしゃくしゃのポケットから出すのは絶対NG
- バッグから出すときも、他のものと混ざらないように
- 封筒は折らずに、そのままきれいに取り出す
所作の目的は、“自分が主張するため”ではなく、相手に敬意を伝えるため。
だからこそ、ちょっとした動きに「気遣い」が滲み出るのです。
🗣 渡すときのひと言が「気持ちの伝わり方」を左右する
そして忘れてはならないのが、言葉の添え方。
せっかく準備した寸志も、無言で渡してしまっては、「これ何?」と思われて終わりかもしれません。
ここでは場面ごとに使える実践的なフレーズをいくつかご紹介します。
✅ 社内イベントや幹事への寸志
- 「今日はありがとうございます。ほんの気持ちですが、お納めください」
- 「お手数おかけしました。ささやかですが、皆さんで使ってください」
✅ 退職する上司や先輩へ
- 「ご指導いただきありがとうございました。ささやかですが、感謝の印です」
- 「長い間お世話になりました。こちら、皆で用意しました」
✅ 手伝ってくれた同僚・社外の方へ
- 「このたびはご協力ありがとうございました。ほんの気持ちです」
- 「大変助かりました。わずかですが、お礼の品です」
🔹 ポイントは、「ささやかですが」「気持ちばかりですが」など、
控えめな表現で、こちらの謙虚さを伝えることです。
❌ やってしまいがちなNG渡し方
最後に、気をつけたい「印象を下げてしまう渡し方」をチェックしておきましょう。
| NGパターン | なぜNGか |
|---|---|
| ポケットから無造作に出す | 準備のなさ・雑さが伝わる |
| 名前をその場で書き足す | 事務的すぎて“気持ち”が見えない |
| 封筒の種類が場に合っていない | 相手に「雑な印象」を与えてしまう |
| 混雑している場面で無理に渡そうとする | 空気が読めていないと感じられる |
| 封筒を裏向きに渡す | 配慮の欠如。礼儀として不適切 |
寸志とは“心ばかり”のもの。
だからこそ、形式の丁寧さが、気持ちの丁寧さに直結するといっても過言ではありません。
✅この章のまとめ
- 寸志は、始まりか終わりの“静かなタイミング”で渡すのが理想
- 封筒の扱いや姿勢で「丁寧さ」が伝わる。両手&お辞儀は基本
- 言葉を添えることで、封筒の中にある“気持ち”が初めて伝わる
- 雑に見える所作や不用意な行動は、好意の逆効果になり得る
🖋 第7章:まとめ:名前の有無より大切なのは「気持ちの伝え方」だった

寸志をめぐる迷い——
「名前って書くべき?」「封筒はこれで合ってる?」「渡すタイミングは?」
今回の記事では、そんな疑問に一つひとつ実践的に答えてきました。
ここで、あらためてお伝えしたいことがあります。
それは、“寸志のマナーに絶対の正解はない”ということ。
なぜなら、寸志とは形式ではなく、人と人との間にある“気持ち”を形にしたものだからです。
“相手にどう気持ちが伝わるか”
寸志に込めるべき心のあり方を再確認していきましょう。
🎯 書くか、書かないか——正解は“相手に合わせる”こと
「社内イベントでは名前は書かないのが礼儀」
「弔事では名前は絶対に必要」
「町内会は書いたほうが親切だけど、地域差もある」…
こうして整理してみると、ルールよりも大事なのは、“相手がどう感じるか”だということに気づきます。
つまり、「この人に、この場面で、どうすれば気持ちが一番伝わるだろう?」
——そうやって考えることが、寸志における最上のマナーなのです。
🪶 気遣いは、形式を越えて伝わる
たとえ封筒に名前が書いていなくても、
- 受け取りやすいタイミングでそっと渡された
- 中袋に小さく名前が書かれていた
- 一言「いつもありがとう」と添えられていた
そんな配慮があれば、寸志は十分に“心ある贈り物”になります。
逆に、表書きが完璧でも、
- 渡すタイミングが空気を読めていなかった
- 手渡しが雑だった
- 無言で渡された
こうした態度では、「気持ち」は伝わりません。
寸志における最上のルールは、“形式を守ること”ではなく、“気配りを尽くすこと”。
それが、マナーに厳しい中高年世代にも、若手社員にも、町内のご年配にも、共通して伝わる「思いやり」のかたちです。
💬 「気持ちの伝え方」3つの心得
最後に、迷ったときに立ち返ってほしい「3つの心得」をお伝えします。
① “相手の立場”に立って考える
→ 上司、部下、社外、地域…相手の受け取り方を想像する。
② “空気を読む”
→ 場の雰囲気・タイミングを見極めることも立派なマナー。
③ “ていねいに、さりげなく”
→ 自分が前に出るのではなく、相手を思いやる所作を大切に。
✅ 総まとめ:寸志マナーの判断ガイド(保存版)
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 表書きの選び方 | 寸志=目上/御礼=万能/松の葉=丁寧な配慮 |
| 名前を書くかどうか | シーンによる。社内イベントでは書かない、弔事や個人宛は書く |
| 渡すタイミング | 会の始まる前または終わり。混雑・盛り上がり中は避ける |
| 渡し方の基本所作 | 両手・お辞儀・ひと言が基本セット |
| 名前を書かない対策 | 中袋記名/メモ同封/口頭での一言でカバー |
🌸 最後にひとこと
“寸志”とは、ほんのわずかな金額かもしれません。
けれど、そこに込められた「ありがとう」の気持ちは、何倍もの信頼や好印象となって返ってきます。
大切なのは、“かたち”より“こころ”。
どうぞ、自信をもって、あなたなりの寸志を届けてみてください。
それが、相手との関係をより深く、心地よいものへと育ててくれるはずです。