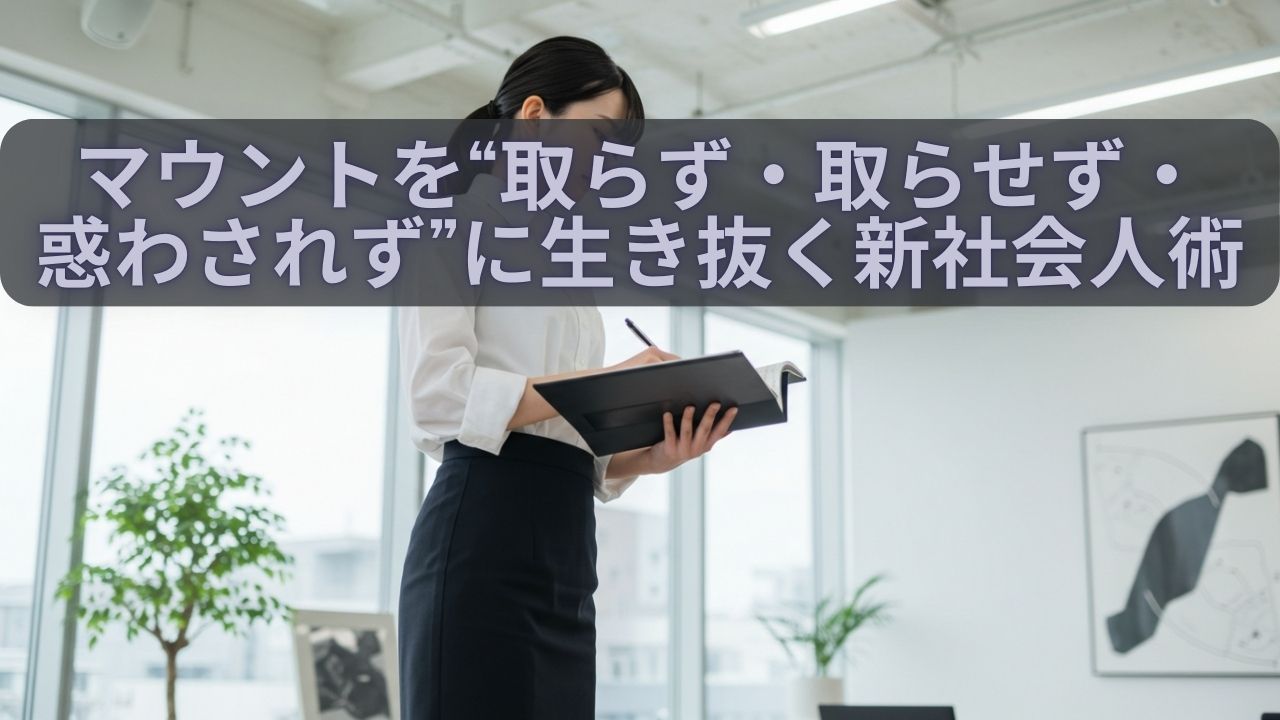「マウントを取る人」と「マウントを取らない人」の違い。
そして、どちらの側にもなってしまう“人間の本能”に、気づかされました。
この記事では、私が出会った多くの人たちとの関わりから見えてきた、
「マウントに振り回されず、自分らしく生きるためのヒント」を、
今まさに社会に出たばかりのあなたへ伝えたいと思っています。
毎日がルーティンのように見える会社生活の中で、実はたくさんの“出会い”と“学び”が積み重なっていました。
上司、部下、取引先、同期、後輩…
仕事のスキルや知識よりも、人とどう向き合うか、どう関わるかに悩み、考え、成長してきた30年だったように思います。
そんな私の経験から感じたことを添えながら、お伝えします。
STEP1:なぜ“マウントを取らない人”は無敵なのか?

〜比較の罠から抜け出して、“自分だけの軸”を築く方法〜
──比較地獄を泳ぎ切る“静かな強さ”の正体
「マウントを取らない人」は、なぜか好かれる。
社会人になりたての頃って、どうしても“周囲との比較”に振り回されがちです。
同期と給与を比べたり、上司に褒められている人を羨んだり、SNSでキラキラしてる同級生を見て落ち込んだり…。
でも、そんな中で「いつも自然体でいられる人」がたまにいますよね?
誰かと張り合ってるわけでもないのに、なぜか存在感がある。
出しゃばらないのに信頼されてる。
“無敵”という言葉が、妙にしっくりくるあの感じ。
その人たち、実は“マウントを取らない人”なんです。
静かに強い人の共通点は「比べない」じゃなく「比べなくていいほど満たされてる」
マウントを取らない人って、他人のことをどうでもいいと思ってるわけじゃありません。
むしろ、他人の頑張りも素直にリスペクトしてる。でも、“自分を上に見せよう”という発想自体がないんです。
これは、実はすごいこと。
なぜなら、私たちは人間である以上、他人と比較する本能を持ってるから。
だから、それをしていない人たちは「偉い人」なんじゃなくて、「もう比べる必要がないほど、自分の軸がある人」なんです。
たとえばこういう人たち。
- 自分の小さな成功をちゃんと見てあげられる
- 誰かの評価より、「自分が納得してるか」を大事にしてる
- 他人のすごさを認められるだけの“心の余白”がある
つまり、外に向かって“すごいでしょアピール”をしなくても、自分の価値をわかっている。
それが、あの「静かに強い」感じの正体です。
自己肯定感と“他人への無関心”の絶妙なバランス
よく「自己肯定感が高い人はマウントを取らない」と言いますが、正確には“他人のことに興味がなさすぎず、執着しすぎない人”なんですよね。
要はバランス感覚がある。
たとえば、職場で「○○さん、すごいよね~」って話題が出たときに、「あー、確かにすごい。私はまだまだだな」と素直に言える人。
こういう人は、劣等感じゃなく“学び”として他人を見るクセがついてるんです。
逆に、心のどこかで「自分もすごく見られたい…」って焦ってると、つい張り合ったり、斜に構えたりしちゃう。
そこにマウントが入り込む余地が生まれる。
マウントを取らない人は、この“比較するスキマ”自体がとても小さい。だから、余計な戦いが始まらないんです。
新社会人にありがちな“無意識マウント”を見破る目を養う
新社会人の時期って、「自分の居場所をどう作るか」に悩みがち。
だからこそ、“マウントの誘惑”に引っ張られやすい。
たとえば、こんな会話、心当たりありませんか?
- 「え、まだその仕事やってるんだ? 自分はもう次のステップいってるけど」
- 「○○社って待遇いいよね。うちは微妙だけど…まあ裁量大きいからさ」
- 「週末ヒマでさ〜、てか普通に読書してた。意識高すぎって言われそう(笑)」
↑これ、全部マウントです。しかも“無自覚な”。
新社会人にとって、こういう言動を「悪気なくやっちゃうこと」がよくあります。
むしろ、そういう空気に染まっていない人は貴重なんです。
マウントを取らない“無敵な人”になるには、まず自分がどんな言葉に引っかかるのか、どんなときに「比べようとしてる自分」が顔を出すのか――そこに気づくことから始まります。
「勝ち負け」から距離を置いた瞬間、人間関係がうまくいき始める
マウントを取らない人が強いのは、“争わないことで勝ってる”からです。
張り合わない。 見下さない。 優劣に反応しない。
これは、単なる“いい人”ではなく、確固たる意志なんです。
だからこそ周囲は安心し、信頼を寄せる。
その人自身も、他人との距離感がちょうどよくなって、人間関係で消耗しにくくなります。
社会に出て、比較という渦に飲まれそうになったら、思い出してください。
「マウントを取らない」って、実はものすごく戦略的な“処世術”なんです。
STEP2:「他人と比べない」は本当に可能?

──理想論ではなく、リアルな解像度で語る“比較”との付き合い方
「他人と比べるな」って言うけど、無理じゃない?
自己啓発本やネット記事でよく目にするフレーズ。
「他人と比べるな。比べるなら、昨日の自分と比べろ。」
…これ、正論だけど、ちょっとしんどくないですか?
なぜなら、人間は本能的に「比較する生き物」だから。
自分の立ち位置を確認するために、無意識に他人を見てしまう。これはある種の“生存戦略”でもあるんです。
だから、「他人と比べないこと」がゴールではなく、
**“比べすぎないこと”“比べても振り回されないこと”**のほうが、現実的な目標なんですよね。
SNSは“比較のインフラ”だと割り切る
特に新社会人になると、SNSで他人の近況を見る機会が爆増します。
- 同期が昇進した
- 友人が海外出張してる
- 先輩が「結婚しました」報告してる
- 知り合いが「転職成功しました」ポスト連投中
もはやSNSは、**“比較という名のマラソン大会”**みたいなもの。
しかも、ゴールがないし、コースも人それぞれ。
ここで重要なのは、“比較しないようにする”ではなく、
「あ、今ちょっと比較しちゃってるな」と気づく力を持つこと。
そのうえで、「でもそれは“あの人のコース”だし、自分は自分で別ルートだから」とリセットできる柔軟性があるかどうか。
比較は勝手に始まる。
でも、終わらせるのは自分次第なんです。
「昨日の自分と比べろ」論の難しさ
もちろん、「他人じゃなくて昨日の自分と比べよう」という考え方は正しいし、美しい。
でも、これって思ってる以上に難しい。
なぜかというと、**「昨日の自分をちゃんと覚えてない」**から。
昨日より成長したかなんて、1日じゃわからないし、
そもそも自己評価が厳しい人ほど「まだまだ」と思ってしまう。
だから、「昨日の自分と比べる」は、“やれたらかっこいいけど実践難易度高め”のワザ。
それよりもおすすめなのは、「自分はどんなことをしてるときに満たされるか?」を知っておくこと。
比較ではなく、“満足度の高い瞬間”に軸を置く。
例:
- 「自分なりに工夫したことが評価されたとき」
- 「丁寧に作業して結果が出たとき」
- 「人に感謝されたとき」
他人のスペックと比べるんじゃなくて、**“自分の満足基準”**で物事を見る癖をつけていくと、自然と比較の波に呑まれにくくなります。
比較を“悪”とせず、使い方を変える
ここで、サブコンテンツからの視点も取り入れておきましょう。
マウンティング研究家によると、比較をゼロにするのは不可能。
だったらむしろ、**「比較をどう使いこなすか?」**が問われてくる、と言います。
マウンティング欲求って、突き詰めれば“向上したい”っていう気持ちの裏返しなんですよね。
だから、「あの人すごいな、くそ悔しい」って思う瞬間を、
そのまま嫉妬で終わらせるんじゃなくて、「どうやったら近づけるかな?」と変換できるかが大事。
マウンティングの土俵から降りて、そこを“学びの観察席”に変えるんです。
嫉妬心は消せない。でも、方向を変えることはできる。
「比べるな」じゃなくて「振り回されるな」
結論として、「他人と比べるな」というアドバイスを、
一度**“実践不可能な理想論”として疑ってみる**のは、とても大切です。
そのうえで、
- 比較は勝手に起こるものだと受け入れる
- 比較に飲まれない軸を、日々の中で育てる
- マウンティング欲求を否定せず、自分の成長に使う
これらを意識するだけで、“比較地獄”から一歩抜け出すことができます。
他人との違いに敏感なあなたへ。
その敏感さを、攻撃や防衛に使うのではなく、「成長のためのセンサー」として活かす。
それこそが、マウントに振り回されずに生きるための第一歩です。
STEP3:“取る側”にも“取られる側”にもならない技術

──SNS・職場で「不毛な競争」に巻き込まれない立ち回り
気づかぬうちに「マウント地雷」を踏んでない?
「マウントって、なんかイヤなこと言ってくる人でしょ?」
…って思ってるそこのあなた。
実はその“何気ないひと言”、あなたがマウントを取る側になってるかもしれません。
そして逆に、自分がマウント取られやすいタイプだとしたら――
あなたの中にも、無意識に“勝ち負けの感度”が高まっているサインかも。
マウントの世界において、「悪者」はいません。
でも、“巻き込まれる人”には共通の特徴があるんです。
この章では、自分も他人も疲弊させない
“マウント回避力”を身につけていきましょう。
【1】共感ファーストの会話が、最強のバリアになる
マウントを取る人の典型パターン、それは:
「あなたの話に“自分語り”をねじ込んでくる」
たとえばこんなやつ↓
A:「昨日ようやくプレゼン資料完成して…」
B:「あーそれ、俺もこの前3時間で終わらせたやつだわ」
これ、何がいけないかというと、**“相手の話を奪っている”**んです。
しかも、自分のすごさをさりげなく添えて。
マウントを回避したいなら、まずやるべきはたった1つ。
「共感が先。自分の話は後。」
A:「昨日ようやくプレゼン資料完成して…」
B:「おつかれ!それ大変だったでしょ〜、何が一番苦労した?」
→この返しができれば、“会話のキャッチボール”は成功です。
これだけで、相手は安心するし、「あ、この人とは戦わなくていいんだな」と思ってくれる。
マウントを生まない空気は、こういう小さな返し方から始まるんです。
【2】「違い」を楽しむセンスが、競争を和らげる
次に大事なのは、「比較を“勝ち負け”に変換しない感性」。
人はどうしても、自分と違う人を見ると、
- 「こっちの方が上?」
- 「あっちはダメ?」
- 「負けてる?」
といった“無意識の優劣フィルター”を通してしまいます。
でも、マウントを取らない人って、それやらないんですよ。
むしろこう考えます:
「へ〜、そういう人もいるんだ。なんか面白いな」
“違いを勝敗で測らない”って、言うのは簡単だけど、やるのはむずい。
だからこそ、ちょっとだけ言い方を変えることがコツ。
✕「え、それって効率悪くない?」
→〇「なるほど、そんなやり方もあるんだ!」
✕「その選択、自分ならしないな…」
→〇「そこに決めた理由、興味あるなあ」
たったこれだけで、会話の雰囲気はガラッと変わります。
違いを尊重できる人には、マウントも嫉妬も生まれにくい。
**「私とあなたは違う、だからいい」**という前提を、空気にのせておきましょう。
【3】「境界線がある人」は、マウントされにくい
マウントを取られる人に多いのが、「いい人過ぎる」タイプ。
- 相手の自慢話を否定せず全部聞いてあげる
- 自分の成果はあまり言わず、謙遜しすぎる
- 自分の気持ちより、場の空気を優先してしまう
これ、実は**“マウントを許可してしまっている”**とも言えます。
だからこそ必要なのが、「心の境界線」。
これは「冷たくなる」とか「突き放す」という意味じゃありません。
**“自分の価値観や時間を守る線引き”**のこと。
たとえば:
- 他人のアドバイスを、すぐ鵜呑みにしない
- 自慢話が始まったら、「そっか〜」でサラッと流す
- 嫌な空気を感じたら、別の話題に切り替える
「誰とでも対等に話す」=「誰にでも付き合う」ではない。
**“私には私のペースがある”**と態度で伝えられる人は、自然とマウントの矛先から外れていくのです。
【4】“無意識のマウント癖”を直す簡単セルフチェック
そして最後に、これも大事。
「自分はマウントなんてしてない」と思ってる人ほど、
実は“気づかないうちに取ってる”こと、多いです。
次の質問、いくつ当てはまりますか?
- 自分の成功体験を話したくなることがよくある
- 「自分の方が詳しい」と思ったときに口を出しがち
- 相手の話より、自分の話の方が面白いと感じる
- 「自分だったらこうするのに」と思いがち
全部が悪いわけじゃないですが、“話の主導権を握りたがる癖”があれば要注意。
ちょっとした言い方や反応で、「相手にマウントだと感じさせる」リスクはあるんです。
だからこそ、意識したいのは、
- 一呼吸置く
- 共感を先に出す
- 自分の話は“聞かれたとき”に話す
この3つを意識するだけで、「マウントを取る側」に無自覚でなってしまうことをかなり防げます。
“中立”をキープする人が、最強に信頼される
新社会人のあなたが身につけたいのは、
マウントを取る側でも、取られる側でもない“第3の立ち位置”。
- 共感のキャッチボールがうまい
- 違いを評価できる
- 自分のペースと価値観を保てる
- 自慢話にはノらず、引かず、流せる
これって、すべて“社会で信頼される力”なんです。
マウントは、気づけばどこにでもある。
でも、戦わず、煽らず、巻き込まれずにスルッとかわす人こそ、
長く、ラクに、信頼されて生きていける。
だからこそ、今このタイミングで「マウントに振り回されない人間力」を育てておきましょう。
STEP4:マウンティング欲求は“悪”じゃない

──比較本能を“自己成長エンジン”に変えるマインドシフト
「マウント=悪」って、ほんとにそう?
「マウントってウザいよね」
「マウントしてくる人って、自信ないんでしょ?」
「私は絶対マウントなんか取らない!」
……はい、その気持ち、わかります。
でもちょっと待って。
マウントを“悪者扱い”しすぎていない?
人は、誰しも“他人よりちょっとでも上にいたい”という欲を持っています。
それは自然なこと。だって、人間は社会的な生き物だから。
「マウンティング=人間の本能」だとしたら、
その本能を否定するよりも、うまく使いこなした方がラクじゃない?
この章では、“マウント否定派”を一歩卒業して、
**「マウンティング欲求を味方につける」**という考え方にシフトしていきます。
マウンティング=向上心の裏返し?
嫉妬や競争心って、たしかに疲れる感情。
でも実は、それって**“成長したい”という欲望の裏返し**でもあるんです。
たとえば、こんな気持ちになったことありませんか?
- 「同期が昇進したって…くそ、悔しい…」
- 「友達のSNSがキラキラして見える。なんで私だけ?」
- 「○○さんに“できる人”って思われたい」
これって、すべて“自分の中に火をつけるガソリン”になります。
誰かのすごさを見てモヤモヤするって、
裏を返せば「自分もそうなりたい」って思ってる証拠。
つまり、マウンティング欲求には“行動エネルギー”としてのポテンシャルがある。
問題は、
「それを他人を下げる方向に使うか」
「自分を伸ばす方向に使うか」
というだけの話なんです。
嫉妬を“比較”じゃなく“目標”に変換する
マウントを生まない思考法の一つに、
**「比較の方向転換」**があります。
例えば:
- 「あの人ばかり評価されて悔しい」
→「じゃあ、自分が評価されるにはどんな行動をすればいい?」 - 「あの子のライフスタイルがうらやましい」
→「私はどんな生活を送りたい?どこが心地いい?」
このように、外に向いているエネルギーを、内側に戻してあげるんです。
これは、自己啓発とかポジティブ思考の話じゃなくて、
“比較本能の使い方”を変える技術。
マウンティング欲求は、無理に消す必要なんてない。
それを**「人を蹴落とす武器」ではなく、「自分を進めるツール」**に変えればいいだけなんです。
欲望は捨てずに“調理法”を変えろ
マウンティング研究家の分析によれば、
人間の欲求は「手放す」のではなく「調理法」を変えるべきだとされています。
たとえば、次のような“調理”ができれば、マウンティング欲求は立派な栄養素になる。
| 欲求のタイプ | 暴走すると | コントロールすると |
|---|---|---|
| 認められたい | 承認欲求モンスター化 | 成果をシェアして、周囲に貢献 |
| 勝ちたい | 攻撃的になる | 比較せずに、自分の成長に集中 |
| 上に立ちたい | 他人を見下す | チームをまとめるリーダー力になる |
ポイントは、
**「欲求そのものは悪じゃない」**という事実に気づくこと。
大事なのは、“どこで”“どんなふうに”使うか。
それだけなんです。
「達観キャラ」は意外としんどい。だから素直になろう
最近の若い世代では、“欲望を持つのがダサい”みたいな空気もありますよね。
- 競争しない方がかっこいい
- マイペース最強主義
- 他人と張り合うなんてナンセンス
たしかにそれも一理あるけど、
本音では「評価されたい」「勝ちたい」と思ってる人も多いはず。
そこで無理に“達観キャラ”を演じようとすると、
どんどん欲求がこじれて、逆にマウンティング爆発…なんてことにもなりかねない。
だから、まずはこう言えるようになろう。
「うん、私だって、たまには人より優れていたいと思うよ。でもそれって、悪いことじゃないよね」
この自己認識を持つだけで、他人に対しても自然と寛容になれるし、
マウントを見ても「はいはい、今ちょっと頑張ってるんだな」で済ませられるようになります。
本能は消せない。でも、味方にはできる。
「マウンティング欲求は敵だ」
「比べるな、欲しがるな」
そうやって否定し続けるよりも、こう考えてみてください。
「欲求は、使い方を間違えると毒になる。でも、正しく使えば栄養になる」
自分の中にある“悔しさ”“嫉妬”“上を目指したい気持ち”。
それを恥ずかしがらずに受け入れて、整えて、育てていく。
マウントを「しない」人の多くは、実は、
**「マウンティング欲求と仲良くなった人」**なんです。
STEP5:誰からもマウントされなくなる“自分ポジション”の作り方

──「あなたはあなた」で強くなれる、“比較されない立ち位置”とは
比較から逃げるのではなく、「比べられない場所」に行け
社会に出て数年経つと気づきます。
**「どこまで行っても、上には上がいる」**ってことに。
学歴、仕事、恋愛、ライフスタイル、SNSのフォロワー数、センス、収入、顔、ファッション……
あらゆる指標で「上」から「マウント」が飛んでくる。
じゃあどうする? 戦う? 逃げる?
実は、第三の選択肢があります。
それが、**「自分だけのポジションを確立する」**ということ。
つまり、**“比較できないポジション”に立つことが、最強のマウント回避策”**なんです。
他人と同じ土俵に乗らないと、マウントは届かない
「比較されるのがつらい」
「何をしても、誰かのほうが上に感じる」
そんなときは、あなたが誰かと同じ“勝負の土俵”に立ちすぎてるかもしれません。
たとえば:
- 同期と昇進スピードを比べる
- SNSで“キラキラライフ”を演出しようとして疲れる
- 友人の恋愛・結婚報告に焦る
でもそれって、「自分が選んだ土俵」ではないかもしれない。
マウントの標的になりたくなければ、土俵をズラせばいいんです。
つまり、「人と違うルールで生きる」。
たとえば…
- キャリアより“生活満足度”を軸にする
- 評価より“楽しさ”を最優先にする
- 資格より“対人スキル”を磨く
→これだけで、周囲の「比較の物差し」から外れていけるんです。
“多軸人間”は最強。1つの肩書きに縛られない自分を持とう
マウントの土俵って、たいてい「わかりやすい軸」でできています。
たとえば:
- 年収
- 学歴
- 見た目
- 勤務先
- フォロワー数
こうした**“一軸”の世界で戦おうとすると、どうしても比較されやすい**。
そこで意識したいのが、“多軸思考”。
自分を「1つの価値観」で説明しない。
例:
- 「中小企業の営業」×「地域でラジオDJもやってる」
- 「大学はFラン」×「起業して年商1000万」
- 「IT企業勤務」×「書道8段で毎週教えてる」
このように、異なる2〜3の要素をかけ合わせると、誰とも被らない“自分だけの輪郭”が浮き上がるんです。
そして、それが“比較されない立ち位置”になります。
自分の「物語」と「武器」を持つ
マウントに強い人は、どこかで“自分だけのストーリー”を語れる人です。
つまり、「なぜ自分はこの選択をしているのか?」という理由を、自分で理解している人。
たとえば:
- 「大企業じゃなくてあえて中小を選んだ。自分には自由度が大事だから」
- 「昇進よりも“人間関係がラク”な環境を優先した」
- 「表には出さないけど、裏でずっと音楽を続けてる」
こういう“自分だけの物語”があると、周りのマウント発言が「別に気にする必要ないや」と思えるようになります。
さらに、それを支える“武器”があるともっと強い。
- 書く力
- 聴く力
- 思考の深さ
- 小さな得意
- 地味だけど継続してる習慣
それは、どんな小さなことでもOK。
**「私はこれが好き」「これに誇りがある」**という武器があるだけで、他人の評価に依存しなくなっていきます。
“異質さ”を恐れない。むしろ、それが最強の防御力になる
マウントを取られるのが怖くなると、人は「浮かないようにしよう」とします。
でも、それって逆にマウントされやすくなるんです。
なぜなら、「同じ土俵にいる」と認識されるから。
だから、ちょっと異質でもいい。
ズレてるくらいのほうが、他人はマウントしにくい。
例:
- “スローライフ×都心暮らし”
- “バリキャリ×仏教好き”
- “SNS未経験×リアル友だち最強主義”
こういう人って、一見ちょっと浮いてるけど、
不思議とマウントの標的にならないんです。
なぜか?
「どの物差しで測ったらいいかわからないから。」
これが、“比較されない立ち位置”の正体です。
「自分だけのポジション」を確立する3ステップ
最後に、実際に自分のポジションを見つけるための簡単ステップをご紹介。
① 「世間とズレてる」と感じるものを3つ書き出す
(例:朝型じゃない/年収に興味がない/結婚願望がない)
② 自分が「楽しい」と感じる時間を思い出す
(例:人と深く話してるとき/ひとりで旅してるとき)
③ それらを「組み合わせて肩書き化」してみる
(例:社交性ゼロの聞き役/週末バックパッカー兼Excel芸人)
→それが、**あなたの“マウントされないポジション”**になる可能性大。
誰とも戦わない。だから、誰にも負けない。
マウントされることに疲れたなら、
「戦わない」ことを選べばいい。
でもただ逃げるんじゃない。
“自分の土俵”を創ることで、争いから自由になる。
それが、マウントをかわす究極のスキルです。
「他人と比べない」は難しくても、
「他人と比べられない場所に行く」は、あなた次第でできる。
新社会人のうちに、“自分だけの立ち位置”を見つけてしまえば、
この先、どんなマウントもあなたに届かなくなります。
STEP6:比較社会を笑って抜ける

──これからの時代を軽やかに生きるためのマウンティング教養まとめ
「マウントされない人」は、実は“マウントを笑える人”
ここまで読んできたあなたなら、
もう気づいているかもしれません。
マウントに勝つ必要なんて、最初からなかった。
比べられないポジションを見つける。
欲求を味方につける。
自分の軸を持つ。
それだけで、
いつの間にか「マウント合戦の外側」に立てている。
そして、最強のマウント対処法とは何か?
それは――
**「笑ってスルーできる人になること」**です。
比較社会は終わらない。でも、巻き込まれるかどうかは選べる
「社会が変わればいいのに」
「他人がマウントしてこなければ平和なのに」
そう思うこともあるでしょう。
でも残念ながら、
マウントのある世界は終わらないんです。
なぜなら、
人間が生きてるかぎり、“比較”と“欲望”は消えないから。
だけど――
「自分がどう向き合うか」は、100%コントロールできる。
・誰かの言動に反応しすぎない
・見せびらかしには冷静な目を
・他人の基準ではなく“自分の快適さ”で選ぶ
これらを意識するだけで、
マウントはただの“通り雨”になります。傘をさせば濡れずに済む。
これからの時代は、“マウンティング教養”が差を生む
これまでスキルや知識、肩書きが重視されてきた時代。
でもこれからは、
**「人間理解力」や「感情の取り扱い方」**のほうが、よっぽど重要になってくる。
なぜなら、AIでもできることが増えていく中で、
**“人間ならではの心の機微を扱える力”**が問われるようになるから。
その一歩として、マウントを見極める力=**「マウンティング教養」**は、すごく役に立ちます。
- あ、この人は自己肯定感が揺らいでるんだな
- ちょっと自分、嫉妬しそうだな。やばいな〜
- この場は張り合うより、流すのが正解だな
こういう“空気の読み方”や“内省のセンス”を持ってる人は、どんな場所でも好かれ、信頼されます。
言い換えれば――
マウンティングを制する者は、人生を制す。
(いやほんとに)
自分の“ごきげん”を自分で守れる人になろう
最後に、これだけは伝えさせてください。
マウントを受けてモヤモヤするのって、
本当は**「自分の価値が揺らいでる」**ってことなんです。
だから大事なのは、「自分のごきげん」を自分で取ること。
- 今日ちょっと頑張ったな
- 美味しいごはん食べられたな
- 誰かにありがとうって言えたな
そういう、小さな“肯定感の積み重ね”が、
他人の言葉に振り回されない土台になります。
どんなにマウントが飛び交う社会でも、
自分で自分を満たせる人は、最強にごきげんでいられる。
比較の呪いから抜けて、自由に生きよう
ここまで読んでくださったあなたへ。
あなたはもう、
「マウントを取る」でも「取られる」でもない、
**“その外側に立てる人”**になっています。
誰かの“すごさ”を素直に尊敬できる。
自分の“満足軸”をちゃんと知っている。
違いを比べず、面白がれる。
それだけで、
この比較だらけの社会を、軽やかに泳いでいける人になれるんです。
「比べるな」じゃない。
「比べられない自分」を見つければいい。
あなたはあなたのままで、強い。
そして、そんなあなたは、
どんなマウントにも**“微笑みながらスルー”**できるようになるはずです。
まとめ:マウントに振り回されない生き方のために

本記事では、マウントを「取る側」「取られる側」どちらにもならずに、
自分らしく社会を生き抜くためのヒントをお伝えしてきました。
✅ マウントを取らない人は、自己肯定感があり、他人と比べる必要がない
✅ 比較しないは難しくても、「比べられない自分」になることはできる
✅ マウンティング欲求は敵ではなく、使い方次第で味方になる
✅ 共感・境界線・多軸的な生き方が、マウントから自由になるカギ
✅ 自分だけのポジションを持てば、他人の評価に振り回されなくなる
次にやるべきことは?
🔹 まずは「自分だけの軸」を1つ決めてみましょう。
それは価値観でも、習慣でも、小さな得意でもOK。
そこから“比較されない人生”が始まります。
最後にひとこと。
もう、誰かの土俵で戦わなくていい。
あなたはあなたの場所で、ちゃんと輝けます。