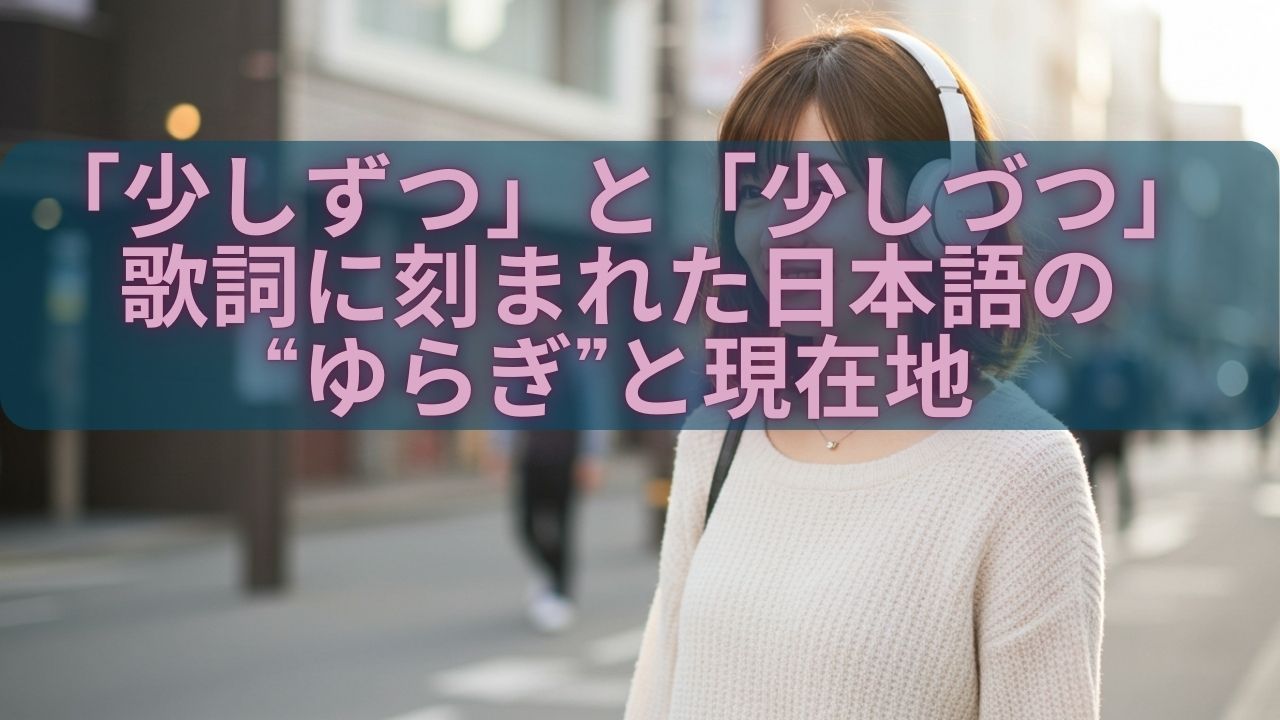「少しずつ? それとも少しづつ?」
普段なんとなく使っているこのフレーズ、どっちが正しいのか迷ったことはありませんか?
現代仮名遣いでは「ずつ」が正解とされている一方で、ZARDの未公開詞から生まれたSARD UNDERGROUNDの楽曲では「づつ」が使われています。
たった一文字の違いに潜む、歴史・感情・表現の奥深さ――
この記事では、言葉の「正しさ」と「自由」のあいだを、音楽と日本語の視点から丁寧に掘り下げていきます。
📝第1章:“少しずつ 少しづつ”のフレーズが心に残る理由
ある日、ふと耳にしたメロディの中に、懐かしさと違和感が同時に宿っている言葉があった。
「少しづつ 少しづつ」。
ZARDの未公開詞をもとに生まれた、SARD UNDERGROUNDのデビューシングル。その曲名を目にしたとき、多くの人が思ったはずだ。
「“づつ”? それって間違いじゃないの?」
でも、間違っていなかった。
そして、ただの“誤用”では説明できない、この言葉の情緒的な力がそこにはあった。
◆ “正しさ”をあえて外した表現の力
SARD UNDERGROUNDがリリースした『少しづつ 少しづつ』は、ZARDのボーカル・坂井泉水が遺した未発表の歌詞による作品だ。
ただのトリビュートではない。これは“言葉を引き継ぐ”という行為そのもの。
その表題に“少しづつ”と、現代の文法上ではマイナーになった表記が選ばれているのは偶然ではない。むしろ、意味と感情を選び取った結果として、“づ”のやわらかさをあえて残したように感じられる。
◆ 「ず」と「づ」はたった一文字の違い。でも、その一文字が空気を変える。
たとえば「ずつ」と「づつ」は、読み方こそ同じでも、見た目に与える印象がほんの少し違う。
- 「ずつ」はシャープで整っていて、どこか無機質。
- 「づつ」は丸みがあり、やさしくて、どこか私的。
歌詞という限られた世界の中では、意味以上に響きやリズム、文字の表情も重要になる。だからこそ、“づつ”という選択がされたのだとしたら……そこに作詞家の音と言葉への感性がにじみ出ている。
◆ ZARDの詞と、それを受け取ったSARD UNDERGROUNDの一年
SARD UNDERGROUND「少しづつ 少しづつ」
実際にその楽曲を受け取ったSARD UNDERGROUNDのメンバーたちは、インタビューの中でそれぞれこう語っている。
「景色が見えてくるような詞で、聴いていて涙が出ました」
「坂井泉水さんの詞を、自分たちの声で届けられることがうれしい」
まだ結成から1年足らずの彼女たちが、過去の大きなレガシーと向き合い、言葉を受け継ぎ、新たな世代に届けていく。そこには、少しずつだけど、確かに前へ進んでいくという想いが込められているように感じられる。
◆ “少しづつ”という選択肢がある時代に生きている
もしこの記事を読んでいるあなたが、「ずつ」と「づつ」のどちらを使うか迷ったことがあるなら、
あるいは無意識に「“づ”って打ってたかも」と思ったなら、それはきっと正しい感覚だ。
なぜなら、今は“正しさ”と“感情”の間で、言葉を選べる時代だから。
この先の章では、そんな「ずつ」と「づつ」の違いや歴史、そして私たちがどう使い分けていけるのかを、少しずつ(いや、少しづつ?)紐解いていこう。
📝第2章:そもそも「ずつ」と「づつ」はどう違う?

コンビニで買ったおにぎりを一口「ずつ」食べるか、「づつ」食べるか。
この場合、どっちでも通じるし、どっちを使っても問題ない。
でも、「言葉って、そもそも何が“正しい”の?」という問いに直面したとき、
このたった一文字の違いが急に深く、そして面白く見えてくる。
◆ まずは結論:現代仮名遣いでは「ずつ」が正解
現在、新聞や教科書、公的な文書などでは一貫して「ずつ」が使われている。
たとえば、「ひとりずつ」とか、「少しずつ配る」みたいに。
これは、「現代仮名遣い」というルールに基づいている。
▪ 「現代仮名遣い」って何?
戦後、1946年に制定された「当用漢字表」と並んで導入された新ルール。
要は「昔の読み方や書き方ってややこしいから、もっと分かりやすくしようぜ」という意図で作られたもの。
それまでの「歴史的仮名遣い」では、「けふ(今日)」や「ぢから(力)」のように、発音と表記にズレがあった。
それをできる限り統一し、「ぢ」「づ」よりも「じ」「ず」を使うように変更された。
だから、「ずつ」が正解。これが今のスタンダード。
◆ でも、「づつ」ももともとちゃんとした日本語
ここで急に、ZARDの世界観が蘇る。
“少しづつ 少しづつ”という歌詞が、なんとなくあたたかく感じたのは、もしかするとこの歴史的仮名遣いの余韻に触れたからかもしれない。
昔の日本語では、「づつ」は完全に日常語だった。
たとえば平安時代の古典『伊勢物語』にも「物を十ばかりづつ持たせて」なんて表現が出てくる。
「づつ」という言葉は、「一つ」「二つ」の“つ”に由来するという説があり、
「〇〇ずつ」と同じくらい、しっかりとしたルーツを持つ表現なのだ。
つまり、「ずつ」は“今の日本語”で、「づつ」は“昔の日本語”。
どちらも、時代ごとにちゃんと居場所がある。
◆ 音の聞こえ方は一緒。でも表記は変化してきた
「ずつ」も「づつ」も、口に出すと違いはほとんどわからない。
それでもなぜ表記だけが変わったのか?
答えはシンプルで、合理化だ。
- 「じ」「ぢ」や「ず」「づ」の使い分けがややこしい
- 多くの人が正しく書けない
- それなら、どちらかに統一した方がいい
ということで、発音が同じなら「じ・ず」にまとめよう、というのが現代仮名遣いの方針。
◆ “づつ”は今も息をしている
とはいえ、「づつ」が完全に消えたかというと、そんなことはない。
歌詞や詩、小説、あるいは個人のブログや日記など、感情を込めたい場所でしれっと登場してくる。
“ずつ”よりも、“づつ”の方がなんとなく柔らかく、丁寧に感じるときがある。
これって、完全に理屈じゃない。感覚の話。
ZARDやSARD UNDERGROUNDの楽曲で“少しづつ”が使われたように、
言葉の世界では、あえて“正解”を外すことで生まれる美しさもある。
◆ 「ずつ」は正しく、「づつ」は自由だ
まとめると、こんな感じになる。
| 表記 | 用途 | 現在の扱い |
|---|---|---|
| ずつ | 公的・公式な文章 | 推奨される現代仮名遣い |
| づつ | 文芸・個人・創作など | 間違いではない、が非主流 |
「づつ」は消えたんじゃない。
ただ、今はちょっと隠れてるだけ。ときどき顔を出して、心を揺らす言葉として使われている。
さて、次章ではそんな“言葉の正しさ”について、もう少し深く掘り下げてみよう。
「正しい日本語」を追い求めることは本当に大切なのか?
その問いに、ちょっとだけ風穴を開けてみる。
📝第3章:言葉の「正しさ」は変わっていく──だから面白い

「“づつ”は間違いです」
「“ずつ”が正しいです」
こんなふうに言われると、つい従ってしまう。
だけどちょっと立ち止まってほしい。
その「正しさ」、誰が、いつ、どこで決めたの?って。
言葉の“正しさ”は、空から降ってくるものじゃない。
時代や人の手によって“少しずつ”書き換えられてきたものだ。
それこそまさに、“少しずつ、少しずつ”と。
◆ 時代によって、正しい言葉は変わる
たとえば、今では「今日」と書くけれど、
昔は「けふ」と表記していた。「けふ会いました」なんて書くと、ちょっと可愛くも見える。
これが、「歴史的仮名遣い」。
そして現代では、読みと一致する「きょう」という形に書き換えられた。
これは、読み手の負担を減らすため。言葉の民主化とも言える。
言葉は生きていて、私たちが暮らす“今”の空気に合わせて変化する。
だから、「正しい」とされる使い方も、時代によって変わって当然なのだ。
◆ 公的と私的──“正しさ”は場によって変わる
じゃあ「ずつ」と「づつ」、どちらを使えばいいのか?
この答えは、“誰に、どこで、どう伝えたいか”によって変わる。
▪ 公的な場なら「ずつ」
役所、ビジネス文書、学校のテスト。
「正確であること」「統一されていること」が求められる場では、「ずつ」が基本。
なぜなら、それが“共通ルール”として認められているから。
▪ 私的な場なら「づつ」もあり
SNS、ブログ、歌詞、小説、手紙。
“気持ち”や“ニュアンス”を優先したい場では、「づつ」も選択肢のひとつになる。
言葉に表情を与えたいとき、“づ”の柔らかさが効いてくる。
◆ 「それ、間違ってますよ」が通じない世界もある
日本語って、ルールがあるようでない世界でもある。
たとえば、
- 「全然大丈夫」
- 「やばい、最高」
- 「うざいほど好き」
これらはかつて“間違った日本語”として否定されてきたが、
今では日常語として完全に市民権を得ている。
「全然」は否定としか使えない? → 今では肯定文でも普通に使う。
「やばい」は悪い意味? → 今では「超いい」という意味でも使う。
つまり、「正しさ」は絶対じゃない。
“多くの人がそう感じる”ことが、新しいルールを作る力になる。
◆ 日本語の“ゆらぎ”が美しい
英語やフランス語のように厳格な文法ルールに縛られていない日本語には、
ある種の「ゆらぎ」と「余白」がある。
「ずつ」と「づつ」の混在は、その象徴のようなものだ。
- 昔の言葉に触れることで、懐かしさが生まれる
- 今の言葉に乗せることで、意味が洗練される
その“あいだ”にあるものこそが、日本語の面白さであり、美しさだ。
◆ 正しさを押しつけすぎると、言葉が息苦しくなる
あまりにも「こうじゃなきゃダメ!」が増えると、
人は言葉を選ぶのが怖くなってしまう。
- 「これで合ってるかな?」と迷いすぎて書けなくなる
- 言葉に感情をのせることが難しくなる
でも、本来の言葉はもっと自由でいい。
特に私的な表現では、“正しさ”よりも“伝わること”の方が大切だ。
「づつ」にこだわる人がいたとしても、それを頭ごなしに否定しないでほしい。
もしかするとその人は、言葉に“気持ち”を込めているのかもしれないから。
「ずつ」と「づつ」。
この2つの間には、ほんのわずかな違いしかないけれど、
その違いが、言葉の世界に深みを与えてくれる。
次章では、そんな“違いを許容すること”について、もう少し掘り下げてみよう。
📝第4章:“間違いじゃない”が持つ許容と余白
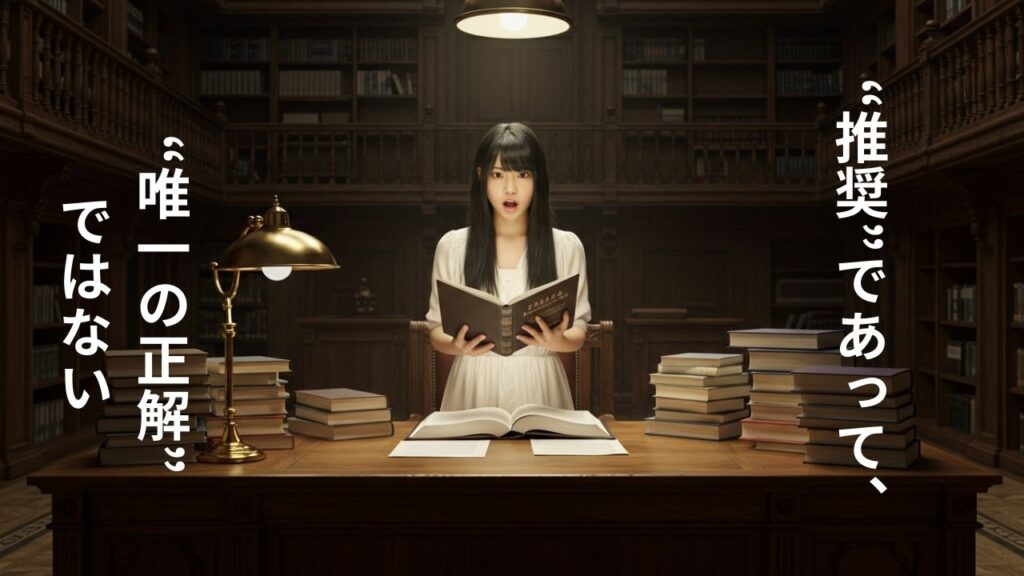
ある日、ある人がツイートしていた。
「“少しづつ”って書いたら、知らない誰かに“間違ってますよ”ってリプされた。
でも、私は“づつ”が好きなんです。」
これを読んで、ちょっと考えてしまった。
正しさとは何か? 間違いとは何か?
そして――“好き”という感情は、言葉を選ぶ理由にならないのだろうか?
◆ 「間違いではない」って、強い言葉だ
「少しづつ」は間違いなのか? 答えはNo。
たしかに「現代仮名遣い」においては「ずつ」が推奨されている。
けれど、それは“推奨”であって、“唯一の正解”ではない。
実際、1986年の国語審議会の見解にはこうある。
「分割しにくい語では『じ』『ず』の使用を基本とするが、『ぢ』『づ』の使用も認められる」
つまり、「少しづつ」は間違いではない。
この“間違いじゃない”という曖昧な肯定が、言葉の世界をどこまでも広げてくれる。
◆ 正解がひとつじゃないからこそ、言葉に感情がのる
たとえば、あなたが誰かに手紙を書くとしよう。
「少しづつでも、あなたの夢が叶いますように」
この一文に、「ずつ」ではなく「づつ」を使った理由は、きっと説明できない。
けれどそこには、“硬くなりすぎたくない”とか、“やさしく伝えたい”という
気持ちの揺らぎがあるはずだ。
ルールではなく感情で選んだ言葉が、読み手の心にスッと入っていくこともある。
言葉はただの道具ではない。人と人の間に流れる温度を持っている。
◆ ルールより“伝わるかどうか”を大切にする時代
SNSの普及や個人発信の時代になってから、「言葉の使い方」は大きく変わってきた。
- 語尾を伸ばしたり
- 小さい「っ」を連打したり
- 絵文字や顔文字で補足したり
これはもう、完全に文法の外にある。
けれど、「伝わってる」よね? っていう世界。
同じように、「ずつ」でも「づつ」でも、“伝わる”ならそれでいい。
むしろ、選べる自由があるからこそ、そこに“個性”や“温度”が生まれる。
◆ “正しくない”が生む共感
SARD UNDERGROUNDの『少しづつ 少しづつ』が心に響いたのは、
“未公開詞”というドラマチックな背景だけじゃない。
あの言葉の並びには、“ちょっとだけ正しくないもの”が持つ魅力があった。
それは、まるで人間そのものみたいだ。
完璧じゃない。揺らいでる。ちょっと不器用。
でも、それがリアルで、心に沁みる。
言葉も人も、少しずつ、少しづつ歩んでいく過程にこそ、
“美しさ”や“尊さ”があるんじゃないか。
◆ 誰かの「づつ」を、そっと受け入れる優しさを
たった一文字違うだけで、揶揄されたり、正されてしまうことがある。
でも、そうじゃなくていい。
「そう書きたかったんだな」
「その人にとっては、こっちがしっくり来るんだな」
そう思えることが、言葉を使う人としての成熟なのかもしれない。
“正す”のではなく、“選ばれた理由”に寄り添う。
そんな視点が、これからのコミュニケーションには必要だと思う。
「間違いじゃない」って、なんて心強い言葉だろう。
そして、「少しづつ」でも「少しづつ」でも、
あなたの言葉が、誰かの心に届く日が来る。
次の章では、SARD UNDERGROUNDの歌詞を入り口に、
音楽がどうやって“言葉に魔法をかけてきたか”を見ていこう。
📝第5章:音楽が言葉に与える魔法──歌詞だから選べた「づつ」

言葉を使う上で、「意味」がすべてだと思っていた。
でも、音楽に触れると、その考えがちょっと変わる。
意味以上に響きが大事だったり、
文字面よりも、感情のリズムが優先されたり。
SARD UNDERGROUNDの『少しづつ 少しづつ』を聴いたとき、
「これは“音楽だからこそ選ばれた言葉”なんだ」と感じた。
◆ 歌詞の中の「づ」──それは意図か、感覚か
なぜ「ずつ」ではなく、「づつ」だったのか。
音としての違いは、ほとんどない。
けれど、文字として見たとき、「づ」は少し丸みを帯びていて、
やわらかくて、どこか懐かしい。
この“視覚的な優しさ”は、活字よりも歌詞カードでこそ感じられる。
そして、それが歌と一緒に流れると、聴く人の記憶や感情を引き出す。
「ずつ」ではなく「づつ」。
たった一文字の違いだけど、そこに坂井泉水の詞が持っていた
やわらかな決意や、ひたむきな願いが滲んでいるように感じる。
◆ メロディに合う言葉、それが「づつ」だった
SARD UNDERGROUNDのメンバーが語っていたように、
この楽曲にはDメロという展開がある。ZARDの楽曲ではあまり見られなかった構成だ。
「そこに感情がグッと入り込むんです」
「歌詞とメロディがピッタリで、涙が出ました」
この“感情の高まり”に、**あえて選んだ「づつ」**が呼応しているのかもしれない。
歌詞においては、意味だけでなく、音のやわらかさ、語尾の響き、母音の余韻までが重要だ。
たとえば、「ずつ」と歌うより、「づつ」とした方が、
優しい“う”の音が少し長く残る。
そこに生まれる余白や間が、聴く人の心に静かに浸透していく。
◆ 文字の「正しさ」より、声の「響き」が優先される世界
日本語の音は、繊細だ。
同じ「づつ」でも、歌う人によってニュアンスが変わる。
たとえば、
- サビ前で「少しづつ 少しづつ」と繰り返すことで、
焦らず、ゆっくり進む心情を際立たせる。 - メロディに乗せて発する「づ」の音が、
決して強くならず、やわらかく、優しく響くように歌われている。
文字だけなら「間違い」かもしれないけど、
音楽の中では、それがむしろ“正解”になる。
歌詞って、言葉のルールから一度自由になれる場所なんだと思う。
◆ “づつ”という言葉に込められた、進む勇気
「少しずつ」ではなく「少しづつ」。
この表記を使うとき、多くの場合それは単なる誤植じゃない。
そこには、じんわりとにじむ想いがある。
焦らずに、時間をかけて、でも止まらずに進む。
“少しづつ、少しづつ”というフレーズは、どこか人生の歩みそのものだ。
ZARDの未公開詞から生まれたこの言葉が、
20年以上の時を経て、今また人の心に届いているのは、
まさに“音楽が言葉に魔法をかけた”からにほかならない。
◆ 「づつ」は、声に出して初めてわかる言葉
読むだけじゃ伝わらない。
書くだけじゃ届かない。
声に出して、歌って、はじめて意味が深くなる言葉がある。
「づつ」は、まさにそんな言葉だ。
歌の中で繰り返されることで、
聴く人の心に、音として、リズムとして、思いとして刻まれていく。
それはルールや正誤を超えた、
“感覚の共有”というかたちのコミュニケーション。
音楽が、言葉を解放する。
「づつ」を“正しくないもの”ではなく、“伝わるための選択”に変えてくれる。
次章では、そんな「づつ」と「ずつ」の使い分けについて、
実際の文例やシチュエーション別で、もっと実践的に掘り下げてみよう。
📝第6章:あなたならどっちを使う?文例と使い分けのヒント

ここまで読んで、「結局、自分は“ずつ”と“づつ”のどっちを使えばいいの?」と思ったあなた。
──正直に言って、どっちでもいいんです。
でも、「どっちでもいい」って言われると、一番困りますよね(笑)。
だからこそ、この章ではシチュエーション別にわかりやすく、
使い方の“コツ”と“心の使い分け”をご紹介します。
◆ 【ルールベース編】迷ったら「ずつ」が無難!
まずは基本ルール。
「正しさ」や「公的な使い方」を重視するなら、
すべて「ずつ」で統一するのが安全です。
✅ 使用シーン例
- 学校の作文・レポート
- 就職活動やエントリーシート
- ビジネスメール・提案書
- プレスリリース・新聞記事
✍ 文例:
- 全員に少しずつ資料を配布してください。
- 成果は一歩ずつ着実に積み上げていきましょう。
この場合、もし「づつ」と書いてしまうと、誤字と捉えられる可能性があるので要注意。
◆ 【感情表現編】気持ちを込めたいときは「づつ」がしっくりくる
逆に、感情を込めた私的な文章や、創作・表現の場では
あえて「づつ」を使うと“やさしさ”が滲み出ます。
✅ 使用シーン例
- 恋人へのLINE
- ブログ・エッセイ
- 歌詞・ポエム・小説
- ハンドメイド商品の紹介文
✍ 文例:
- 少しづつ、距離が縮まっていく感じが心地よい。
- 焦らなくていいよ。少しづつで、大丈夫。
- この刺繍も、毎晩少しづつ縫い進めています。
“づつ”のやわらかさには、「急がないよ」「ちゃんと寄り添ってるよ」
というニュアンスが潜んでいます。
◆ 【SNS編】あえて「づつ」を選ぶことで、余韻を演出できる
SNSでは文法よりも感覚がすべて。
あなたの言葉に感情がのっているなら、「づつ」も立派な表現になります。
✅ 投稿例
頑張らなくていい。
進める日も、進めない日も、少しづつ 少しづつ。
コーヒーを片手に、本を少しづつ読む時間が、今の癒し。
ちょっとした一言が、“ずつ”と“づつ”の違いだけで
雰囲気や温度感がまるで変わるのを実感するはず。
◆ 【創作活動編】歌詞や小説では「意味」より「響き」を優先してOK
創作では、「どう読まれるか」より「どう響くか」が命。
「づつ」は意味より感情を重視したいときに向いています。
✅ 使い分けポイント
- キャラクターの性格に合わせて「づつ」を使う
- シーンの雰囲気に柔らかさを出したいときに「づつ」
- リズムや語感の流れが「づつ」の方が心地よいときに選択
たとえば:
少しづつ 少しづつ 僕らは知らない街に馴染んでいった
この1行、もし「ずつ」に置き換えると、
急に“真面目すぎる”印象になるの、わかりますか?
◆ 【感覚で選ぶ編】「どっちが好き?」で決めるのも全然アリ
ここまで実用性だのTPOだの言ってきましたが、
結局いちばんしっくりくるのは、**「自分が好きな方を選ぶ」**です。
- 「づつ」の方がなんか優しい気がする
- 「ずつ」はかっちりしすぎてて合わない
- 両方使って、場面ごとに“空気”を変えたい
──ぜんぶアリです。
誰かの目じゃなく、あなた自身の耳と目と感情にフィットする表現を選ぶ。
それが一番、自然で、伝わる言葉になるんじゃないでしょうか。
◆ 「づつ」は、あなたの“らしさ”が出せる魔法の言葉
「ずつ」はルール。
「づつ」は余白。
だからこそ、「づつ」を使うときって、ちょっと自分の感性を信じる瞬間なんですよね。
もし今、あなたが誰かに何かを伝えたいと思ったとき、
「少しずつ」でも「少しづつ」でもいい。
どちらの表現でも、きっとその想いは伝わります。
大事なのは、どう書くかじゃなくて、何を込めるか。
📝第7章:【まとめ】少しずつ、少しづつ、ことばの世界を味わっていこう

「ずつ」と「づつ」――たった一文字の違い。
けれどそこには、日本語という“生きもの”のような言葉の世界の、
奥深さと自由さがぎゅっと詰まっていました。
◆ 正しさに縛られすぎなくていい
もちろん、「ずつ」が現代仮名遣いにおける正解です。
学校や仕事では、まず「ずつ」と書いておけば間違いありません。
でもそれだけでは、ちょっと物足りないときがある。
特に、感情を伝えたいときや、自分らしい言葉を探しているとき。
そんなときこそ、「づつ」が登場するんです。
それは間違いではなく、あなたの中にある“言葉の感覚”が選んだ表現。
◆ ZARD、SARD UNDERGROUNDが教えてくれたこと
「少しづつ 少しづつ」――この歌詞が美しいと感じたのは、
そこに“誤用”なんて無粋な言葉では言い切れない、詩の力があったから。
ZARDが紡いだ詞を、SARD UNDERGROUNDが継ぎ、
その中にあった“づつ”が、また新しい感情を私たちに届けてくれた。
それはきっと、正しさよりも、想いが選ばれた瞬間だった。
◆ 少しずつ、少しづつでいい
言葉も、人も、急には変われない。
完璧じゃなくていいし、完璧を目指す必要もない。
- 伝えたいけど、うまく言えない
- 書いてみたけど、これで合ってるか分からない
- でも、気持ちはちゃんとある
そんなとき、「少しずつ」「少しづつ」という言葉は、
不思議と寄り添ってくれる。
「いいよ、それで。あせらなくて」
「進まなくても、戻っても、大丈夫」
言葉の“ゆらぎ”は、人間らしさそのもの。
そしてその“ゆらぎ”を認め合える社会こそ、あたたかい。
◆ 言葉を味わう余裕を、今日から少しだけ
この記事を読み終えた今、もしあなたが
文章を書くときや、言葉を選ぶときに、
ふと「ずつ」「づつ」のことを思い出してくれたら嬉しいです。
そして、「こっちのほうが今の気分に合うな」
そう思って選んだ一文字が、誰かの心に届くかもしれません。
正しさを知って、自由を選ぶ。
そんなバランス感覚を、私たちは「少しずつ、少しづつ」
身につけていけるはずです。
さあ、今日もあなたの言葉で、あなたのままに伝えていきましょう。
それが一番、伝わる文章の書き方です。