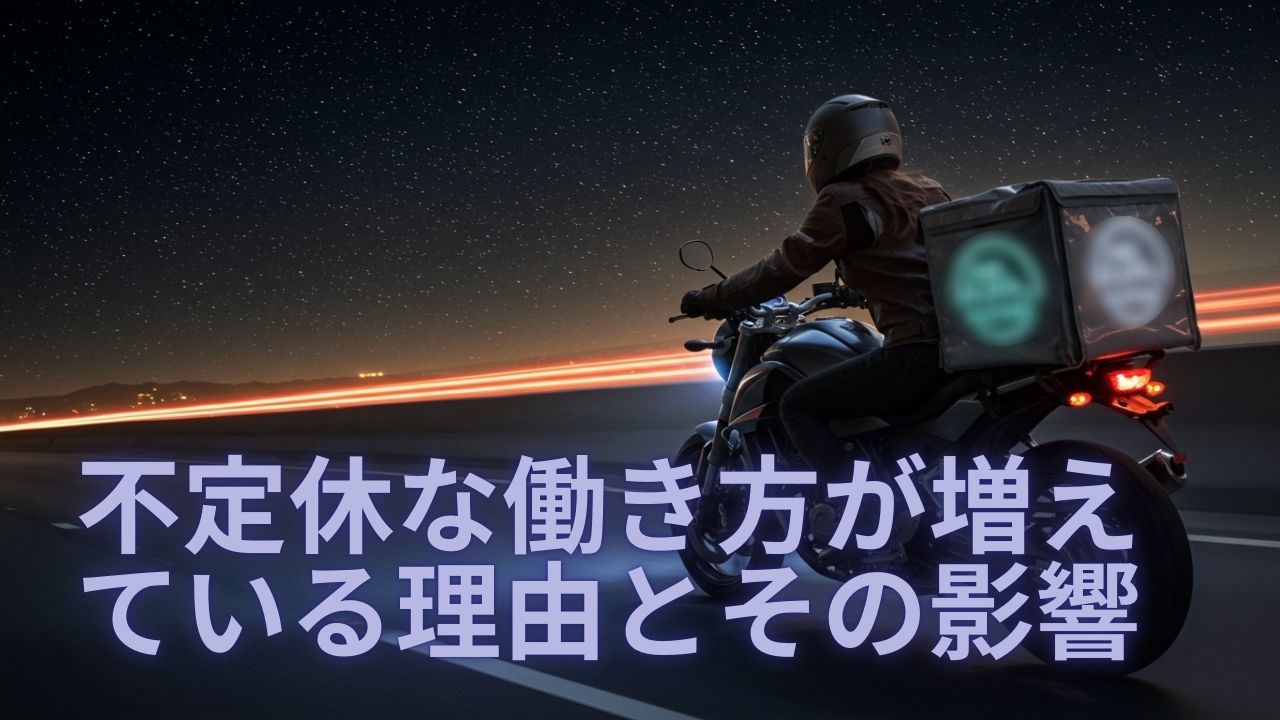「不定休って聞いたことはあるけれど、実際にはどんな働き方なの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?不定休は、特定の曜日や日付に縛られずに休みを取得できる働き方で、特に飲食業やサービス業で採用が進んでいます。繁忙期や閑散期に合わせて柔軟にシフトを調整できるため、企業側にとっても業務効率や収益性の向上につながります。
一方で「予定が立てにくい」「生活リズムが乱れる」といったデメリットも存在します。この記事では、不定休の基本的な意味から、働き方のメリット・デメリット、企業経営への影響、さらには不定休を活用した転職のポイントまでを徹底解説。
不定休を取り入れた働き方が、自分に合っているのかをぜひチェックしてみてください!
不定休の意味とその働き方の解説

不定休とは、特定の曜日や日付に縛られず、業務の状況や個人の都合に応じて柔軟に休みを取る働き方を指します。特に飲食業やサービス業などでは、繁忙期や閑散期に応じて柔軟に休みを調整するケースが多く、不定休の導入が進んでいます。ここでは、不定休の具体的な意味や、定休日との違い、シフト制との関係について詳しく解説します。
不定休とは?基本的な意味
不定休とは、決まった曜日や日付に休みを取るのではなく、業務の状況や個人の都合に応じて休みを設定する働き方を指します。例えば、店舗の混雑状況やスタッフの勤務状況に応じて、柔軟に休みを調整するケースがこれに該当します。
不定休は特に飲食業や小売業、サービス業など、繁閑の差が激しい業界で採用されやすい傾向があります。企業や店舗にとっては、営業状況に応じた最適な人員配置やコスト管理が可能になるため、不定休は重要な経営戦略の一つとなっています。また、不定休を導入することで、従業員にとっても生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になります。
最近では、リモートワークやフレックスタイム制度と組み合わせて不定休を導入するケースも増えています。これにより、従業員のモチベーションや生産性の向上が期待されています。また、不定休を導入することで、従業員のストレス軽減や職場への定着率の向上も見込まれています。さらに、労働時間や休日の柔軟性が増すことで、家庭や個人の事情に合わせた働き方が可能となり、ライフワークバランスの改善につながっています。
不定休を採用する企業側にもメリットがあります。従業員の勤務希望に柔軟に対応することで、長期的な人材確保が可能になり、離職率の低下や採用コストの削減が期待できます。加えて、営業状況に応じた最適な人員配置ができるため、業務効率が向上し、結果的に企業全体の生産性や収益性の向上につながります。
不定休と定休日の違い
定休日は、毎週特定の曜日や日付に固定された休みを指します。たとえば、「毎週日曜日が定休日」のように、曜日が固定されているケースが該当します。また、定休日は顧客にとっても認知しやすく、営業スケジュールが明確になるため、集客やマーケティング戦略を立てやすいという利点があります。
一方、不定休は特定の曜日に縛られず、業務の状況に応じて柔軟に休みを取ることが可能です。不定休の場合、「今週は月曜日と水曜日が休み、来週は火曜日と金曜日が休み」のように、スケジュールが流動的に変わります。このため、繁忙期やイベント開催時には、急な営業時間変更や追加業務への対応が容易になります。さらに、不定休を採用することで、ピーク時には人員を集中配置し、閑散期には人件費を削減するなど、柔軟な営業戦略が可能になります。
不定休のシフト制について
不定休の働き方では、シフト制が採用されることが多いです。シフト制により、勤務時間や休日が柔軟に決められるため、スタッフのスケジュールや業務の都合に応じた調整が可能となります。
シフト制には「固定シフト」と「変動シフト」の2種類があります。固定シフトは毎週同じ曜日・時間に勤務する形式で、安定したスケジュールが維持できます。一方、変動シフトは繁忙期や閑散期に応じて柔軟に勤務スケジュールを調整する形式で、不定休と非常に相性が良い働き方です。
最近では、デジタルシステムやAIを活用したシフト管理ツールの導入も進んでいます。これにより、スタッフの勤務希望や過去の営業データをもとに最適なシフトが自動生成されるため、シフト作成の負担軽減や公平なスケジュール調整が実現可能になります。
また、不定休のシフト制においては、スタッフ同士がシフトを交換しやすい環境を整えることで、急な体調不良や用事が発生した場合にもスムーズな対応が可能になります。
不定休の働き方のメリット

不定休を導入することで、従業員が自分のライフスタイルや業務状況に合わせて柔軟に休みを取得できるため、ワークライフバランスの向上が期待できます。また、繁忙期や閑散期に対応しやすくなるため、企業側にも業務効率や収益性の向上といったメリットがあります。このセクションでは、不定休の働き方がもたらす具体的なメリットについて解説します。
自由な時間管理が可能
不定休を導入することで、個人の都合やライフスタイルに応じて柔軟な働き方が可能になります。自分に合ったペースで働くことができ、ワークライフバランスの向上につながります。特に子育てや介護などの家庭の事情を考慮しながら働きたい人にとって、不定休は理想的な制度となります。
また、趣味や副業との両立も可能になるため、自分らしい働き方が実現できます。近年では、パラレルキャリアや兼業を認める企業も増えており、不定休制度を活用して効率的に時間を使うことで、自己成長や収入アップにもつながります。
さまざまな業務に対応
不定休により、繁忙期や閑散期に対応しやすくなります。状況に応じて休みを調整できるため、業務の効率化や顧客対応力の向上が期待できます。たとえば、飲食業ではランチタイムやディナータイムにスタッフを集中配置し、アイドルタイムには人員を減らすことで、効率的な営業が可能になります。
また、繁忙期に多くのスタッフを投入して対応力を強化し、閑散期には休暇を取りやすくすることで、従業員の負担軽減と業務効率化を同時に実現できます。これにより、サービス品質の向上や顧客満足度の向上にもつながります。
フリーランスとしての活用例
フリーランスや個人事業主の場合、不定休の働き方を採用することで、プロジェクトごとのスケジュールに合わせた柔軟な休暇取得が可能になります。たとえば、プロジェクトの納期に合わせて集中して働き、納品後にまとまった休みを取ることが可能になります。
また、リモートワークや海外での仕事などにも対応しやすくなるため、フリーランスの働き方にとって不定休は大きなメリットとなります。さらに、クライアントの要望に柔軟に対応できることで、仕事の評価や信頼度が向上し、新たな案件獲得にもつながります。
不定休のデメリット

不定休は柔軟な働き方を可能にする一方で、スケジュールが不規則になるために生活リズムが乱れたり、予定を立てにくくなるなどのデメリットもあります。また、繁忙期には従業員への負担が増加することもあるため、適切なシフト管理やフォロー体制が重要です。このセクションでは、不定休のデメリットについて詳しく説明します。
プライベートの計画が立てづらい
休みが固定されていないため、友人や家族との予定が立てづらくなる可能性があります。特に家族や友人が土日祝日に休みを取ることが多い場合、不定休の人がスケジュールを合わせるのは困難です。また、子どもの学校行事や地域のイベントに参加しにくくなるケースもあります。その結果、人間関係に影響が出る可能性もあるため、柔軟な休暇調整が求められます。
従業員の労働負担の増加
シフト制の場合、繁忙期に休みを取りにくくなることがあり、従業員への負担が増すことがあります。特に飲食業やサービス業などでは、繁忙期に十分な人員を確保するために休みが制限されることがあります。また、突発的な業務の発生により、急なシフト変更が求められることもあり、結果として精神的・肉体的な負担が増大する可能性があります。
また、同僚が欠勤した場合に代替勤務を求められることもあるため、休日が急に減るリスクもあります。これにより、過労やストレスの蓄積が起こりやすくなります。
シフトによる時間管理の難しさ
勤務時間や休日が不規則になることで、生活リズムが乱れる可能性があります。特に夜勤や早朝勤務が混在するシフトの場合、睡眠時間が安定せず、体調不良や集中力の低下を引き起こすことがあります。また、一定のリズムが維持できないと、精神的なストレスやイライラが増加し、仕事のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
さらに、不定休によって「休日にしっかり休めない」状況が続くと、疲労が慢性化しやすくなります。これにより、ワークライフバランスが崩れ、仕事へのモチベーションや生産性の低下につながることがあります。
不定休が店舗経営に与える影響

不定休を採用することで、繁忙期や閑散期に応じた柔軟な営業時間の調整が可能となります。また、従業員の負担を軽減しながら業務効率を最大化できるため、企業側にとっても大きな利点があります。ここでは、不定休が店舗運営や顧客対応、従業員のモチベーションに与える影響について詳しく解説します。
顧客対応の柔軟性
不定休を採用することで、営業時間やサービスの柔軟性が増し、顧客満足度の向上につながります。たとえば、繁忙期に営業時間を延長したり、閑散期に営業時間を短縮することで、顧客の需要に応じた柔軟な対応が可能となります。また、急なトラブルや悪天候などで営業時間を変更する際にも、不定休のシステムが役立ちます。さらに、SNSやウェブサイトを通じて営業時間をリアルタイムで更新することで、顧客に対する信頼感も向上します。
業務の効率化とシフト管理
業務の状況に応じてシフトを調整できるため、無駄を減らし、効率的な店舗運営が可能になります。繁忙期には人員を増やし、閑散期には人件費を削減することで、運営コストの最適化が図れます。また、従業員が自分の働き方に合わせてシフトを調整できるため、長期的な人員定着率の向上も期待できます。
さらに、デジタルシステムやAIを活用したシフト管理ツールを導入することで、勤務スケジュールの作成や調整が自動化され、管理者の負担が軽減されます。シフトの不公平感を減らし、従業員の働きやすさが改善されることで、業務効率のさらなる向上が期待できます。
従業員のモチベーション管理
柔軟なシフト制により、従業員が働きやすくなることで、モチベーションの維持や向上が期待できます。不定休を取り入れることで、従業員が自身の生活リズムやプライベートな予定に合わせて働けるようになります。特に、育児や介護などの個人的な事情を抱える従業員にとっては、大きな働きやすさの向上につながります。
また、従業員の意見を取り入れた柔軟なシフト制度や、休暇取得の促進を行うことで、職場への満足度が高まり、従業員の定着率が向上します。さらに、インセンティブ制度やパフォーマンス評価の仕組みを導入することで、仕事への意欲や責任感も強化され、結果として全体の業務効率やサービス品質の向上が期待できます。
不定休の制度と仕事内容

不定休は、特に飲食業やサービス業など、業務の繁閑差が大きい業種で導入されやすい制度です。定休と不定休を組み合わせることで、より柔軟な営業スタイルや従業員の働き方が可能となります。このセクションでは、業種ごとの不定休の導入事例や、シフト管理の方法について説明します。
業種別の不定休の例
飲食業やサービス業など、業務の繁閑差が大きい業種では、不定休が導入されやすいです。
特に飲食業では、ランチタイムやディナータイムなどのピーク時にスタッフを集中的に配置し、アイドルタイムに休みを取ることで、効率的な営業が可能になります。
また、美容業界や小売業でも、不定休を活用することで、顧客の需要に応じた柔軟な営業体制を確保できます。
一方で、医療業界や介護業界では、不定休が導入されるケースも増えています。
24時間体制で患者を受け入れる必要があるため、シフト制と不定休を併用しながら、スタッフの負担を軽減する工夫が求められます。
特に夜勤や長時間労働が発生しやすい業種では、不定休を採用することでスタッフの体調管理や勤務負担の軽減が可能になります。
定休との組み合わせ
定休と不定休を組み合わせることで、業務のバランスを取りやすくなります。
たとえば、週に1回の定休日を設定し、それ以外の日は不定休にすることで、業務の繁閑に応じた柔軟な対応が可能になります。
さらに、従業員のライフスタイルに合わせて定休と不定休を調整することで、従業員満足度やモチベーションの向上が期待できます。
たとえば、週末に家族と過ごしたい従業員には週末に定休を設け、平日に働きたい従業員には平日に不定休を設けるなど、個別対応が可能になります。
このような制度設計により、離職率の低下や従業員の働きやすさの向上が期待できます。
どのようにシフトが決まるか
従業員の希望や業務の状況に応じてシフトを決定するケースが多く、店舗マネージャーが調整役となることがあります。
特に繁忙期やイベント時には、事前にスタッフの希望を聞いたうえで、適切な人員配置を行うことが求められます。
また、シフト管理システムを導入することで、勤務希望の調整や労働時間のバランスをデータに基づいて最適化することが可能になります。AIやクラウドを活用したシステムでは、過去のデータから繁忙期や閑散期のパターンを学習し、自動的にシフトを最適化する機能も利用可能です。これにより、従業員の負担軽減や人件費の効率的な管理が期待できます。
不定休を活用した転職のポイント

不定休を採用する企業が増えている中で、転職時に不定休が自分に合っているかどうかを判断することが重要です。
また、不定休を採用している企業の中には、フレックスタイム制やリモートワークと組み合わせているケースもあります。このセクションでは、不定休を活用した転職活動のポイントについて解説します。
不定休を提案する企業の増加
働き方改革の一環として、不定休を採用する企業が増えています。柔軟な働き方を求める転職者にとって、魅力的な選択肢となっています。
特にIT業界やサービス業では、プロジェクトベースの仕事が多いため、不定休が適しているケースが増えています。
また、リモートワークやフレックスタイム制度と併用することで、さらに柔軟な働き方が実現可能になります。
さらに、企業側としても、従業員の満足度や働きやすさが向上することで、離職率の低下や長期的な人材の確保につながるため、不定休を積極的に採用するケースが増えています。
特に、若年層やミレニアル世代をターゲットとした企業では、不定休を導入することで人材獲得競争において優位性を確保しようとしています。
自分に合った働き方を見つける
不定休が合うかどうかは個人差があるため、自分のライフスタイルに合った働き方を模索することが重要です。
たとえば、趣味や副業に時間を割きたい場合や、家族との時間を重視したい場合など、自分自身の優先事項を明確にすることが重要です。
また、不定休を採用している企業の中には、「完全フレックス制」や「自己申告制のシフト管理」など、さらに柔軟な勤務制度を設けているケースもあります。
そのため、企業説明会や面接で具体的な働き方やシフト制度の詳細を確認し、自分に合った環境かどうかを見極めることが重要です。
転職の際の質問例
- シフトの決定方法は?
- 休暇の取りやすさは?
- 業務量と休みのバランスは?
- 緊急時や繁忙期の対応は?
- 希望する休みや働き方がどれくらい反映されるか?
- 不定休制度に関する具体的な運用方法は?
不定休における休業の重要性

不定休を採用する際には、顧客や従業員への事前の告知が重要となります。休業日を有効に活用することで、業務改善や従業員のスキルアップにつながる可能性もあります。
このセクションでは、休業日の効果的な告知方法や、休業日を活用した業務改善の具体例を紹介します。
休業日のお知らせの具体例
不定休を採用する場合、事前に休業日を告知することが重要です。ホームページやSNSを活用して、顧客への告知を徹底します。
特に、公式サイトやGoogleマップなどのプラットフォームを通じて、営業時間や休業日の更新をリアルタイムで行うことが望ましいです。
また、メールマガジンやLINE公式アカウントを活用して、定期的に休業日や特別営業のお知らせを配信することで、顧客の混乱を防ぐことができます。
さらに、来店した顧客に対しても、次回の休業日を案内したり、店舗内にポスターや掲示板を設置することで、直接的に情報を伝える方法も有効です。
常連客に対しては、会員制度やポイント制度を導入し、事前に営業スケジュールを知らせることで、リピーターの増加にもつながります。
店舗運営における計画の立て方
不定休のスケジュールを従業員と共有し、無理のないスケジュール管理を行うことで、円滑な店舗運営が可能になります。特に繁忙期やイベントが重なる時期には、事前にシフト調整を行い、必要なスタッフ数を確保することが重要です。
また、シフト作成ツールを導入することで、スタッフの希望や勤務状況を考慮した柔軟なスケジュール調整が可能になります。これにより、スタッフ間の不公平感を減らし、勤務環境の改善につながります。さらに、過去の営業データをもとにしたAI分析を活用することで、ピーク時や閑散期に応じた最適な人員配置が可能になります。
店舗運営においては、従業員の満足度を高めることが重要です。例えば、繁忙期にはインセンティブ制度を導入し、モチベーションの維持を図ることが効果的です。また、従業員の休暇希望を優先的に考慮することで、労働環境の改善や長期的な定着率の向上が期待できます。
休業日を利用した業務改善
休業日を利用して店舗の清掃や設備メンテナンスを行うことで、業務効率が向上します。特に、厨房機器やエアコンなどのメンテナンスを定期的に行うことで、トラブルの発生を未然に防ぐことが可能になります。また、店舗の内装やレイアウトを見直すことで、顧客の利便性や店舗の魅力を高めることができます。
さらに、休業日には従業員の研修やミーティングを行うことで、サービスの質を向上させる機会となります。新しい接客マナーや商品知識の共有を行うことで、スタッフ全体のスキルアップが期待できます。定期的な振り返りと改善を行うことで、競合店舗との差別化や顧客満足度の向上につながります。
不定休の英語での表現

不定休を英語で表現する場合、”irregular days”や”flexible holidays”などが一般的です。
英語圏ではフリーランスやパートタイム労働者の働き方に関連して使用されることが多く、ビジネスの場面でも活用されています。
このセクションでは、不定休に関する英語表現とその具体的な使い方について説明します。
“irregular days”の意味
「irregular days」は、不定期に休みを取ることを意味します。
この表現は、特にビジネスや店舗の営業スケジュールに関連して使用されることが多く、決まった曜日に休業するのではなく、需要やスタッフの都合に応じて不規則に休みを取る場合に使われます。
また、英語圏では「irregular days」を用いて、フリーランスやパートタイムの柔軟な働き方を説明することもあります。
例えば、「irregular days」は飲食業や小売業でよく使用され、「Our store is closed on irregular days depending on the business situation.」といった形で、営業状況に応じて休業日が変更される場合を伝える際に使われます。
このため、顧客にとっても「irregular days」という表現を理解してもらうことが重要になります。
英語での使い方例文
- Our store is closed on irregular days depending on the business situation.
- My work schedule includes irregular days off, which gives me flexibility to handle personal matters.
- The company operates on irregular days during the holiday season.
- Many freelancers prefer irregular days to accommodate different project timelines.
言い換え表現の活用
「irregular days」は以下のような言い換え表現が可能です。
- Flexible holidays → 柔軟な休日
- Unscheduled days off → 予定されていない休日
- Random days off → ランダムな休日
- Non-fixed holidays → 固定されていない休日
「Flexible holidays」は、従業員が自身の希望や業務状況に応じて休暇を自由に設定できる場合に使用されます。
「Unscheduled days off」は、特定の曜日に縛られず、必要に応じて取得される休日を指します。「Random days off」は、特に規則性がない場合に使われ、「Non-fixed holidays」は、固定の曜日に休みを取らないという意味で用いられます。
不定休に関連するよくある質問

不定休やシフト制に関する疑問は多く、特にシフトの決め方や有給休暇の取得方法などがよく質問されます。このセクションでは、実際に寄せられる不定休に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
不定期とはどういう意味か?
不定期とは、特定の曜日や日付に縛られず、必要に応じて休みを取ることを指します。
たとえば、飲食業や小売業では、混雑状況や従業員の勤務状況に応じて休業日を柔軟に変更することがあります。
また、プロジェクトベースの仕事では、業務の進捗やクライアントとのスケジュールに応じて、休みの日が調整されることが一般的です。
さらに、不定期な休みは、フリーランスやギグワーカーの間で一般的です。彼らはクライアントのニーズや仕事量に応じて休みを設定できるため、柔軟な働き方が可能となります。
このような柔軟性により、働き方改革の一環として不定期休暇を導入する企業も増えています。
シフト制の働き方についてのQ&A
Q. シフトはどのように決まりますか?
A. 会社や店舗の方針、従業員の希望によって調整されます。特に飲食業やサービス業では、繁忙期や閑散期に応じてシフトが調整されることが一般的です。多くの企業では、デジタルシフト管理ツールを活用して、従業員の希望や店舗の混雑状況に応じて最適なシフトを作成しています。
また、突発的な業務の発生時には、柔軟にシフトを再編成するケースもあります。従業員間の公平性やワークライフバランスを考慮しながら、可能な限り希望に沿ったシフトを組むことが重要とされています。
Q. シフト制での休みはどうなりますか?
A. シフト制の場合、勤務時間や休暇が固定されていないため、特定の曜日や祝日が休みにならないことがあります。
しかし、多くの企業では、繁忙期を避けたオフシーズンに休暇を取りやすくするなど、従業員の負担を軽減する工夫を行っています。
また、事前に休みの希望を提出できるケースも多く、従業員の都合に配慮した柔軟な対応が可能です。
休みを含む仕事の制度について
Q. 有給休暇はどのように取得できますか?
A. シフト制の場合でも、労働基準法に従って有給休暇の取得が可能です。
有給休暇は、法定の日数を満たしていれば、シフト制であっても取得する権利があります。
ただし、繁忙期やシフトの関係で休みが取りにくい場合もあるため、事前に管理者と相談して計画的に取得することが推奨されます。
Q. 有給休暇を取りやすくするための工夫はありますか?
A. 企業によっては、有給休暇を取りやすくするために「有給休暇取得奨励制度」を導入しているケースがあります。
特にシフト制の職場では、従業員が休みやすくなるように、人員配置を工夫したり、有給休暇取得を事前に申請できるシステムを導入していることがあります。
また、業務が落ち着いている閑散期に有給休暇を取得しやすくするなど、従業員が不公平感を感じないような対応も重要となります。
まとめ

不定休は、特定の曜日に縛られずに柔軟に休みを取得できる働き方で、飲食業やサービス業を中心に広く採用されています。
企業側にとっては、人件費や勤務シフトの最適化、従業員のモチベーション向上といったメリットがある一方で、顧客にとって「いつ営業しているかわかりにくい」という課題も存在します。
また、従業員側にも「生活リズムが乱れる」「予定を立てづらい」といったデメリットがあるため、適切なシフト管理や柔軟な調整が重要です。
不定休を活用した働き方を成功させるには、従業員の希望を反映したシフト管理や、事前の営業スケジュールの告知が欠かせません。
企業と従業員の双方にとって最適な不定休の制度設計を行うことで、効率的な運営と従業員の満足度向上を同時に実現できます。
あなたに合った働き方を見つけるために、不定休制度を積極的に取り入れている企業をチェックしてみましょう!